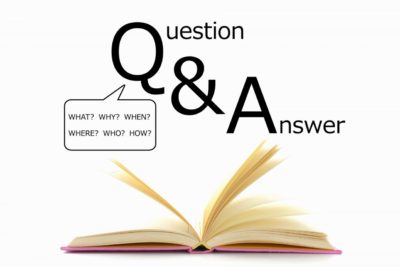帰化申請の費用はいくら?行政書士に依頼するメリットと自分で手続きする注意点を徹底解説
帰化申請サポート

日本での生活が長くなり、「これからもずっと日本で暮らしていきたい」と考えたとき、多くの方が「帰化」という選択肢を検討されるのではないでしょうか。
しかし、帰化申請と聞くと、「手続きが複雑で難しそう」「費用は一体いくらかかるのだろう?」といった不安や疑問がつきものです。特に、専門家である行政書士に依頼すべきか、それとも費用を抑えるために自分で挑戦すべきか、悩まれる方は少なくありません。
ご自身で手続きを進めることで費用を節約できる可能性はありますが、その一方で、膨大な時間と労力がかかるだけでなく、思わぬ落とし穴にはまってしまうリスクも存在します。
こちらの記事では、帰化申請にかかる費用を多角的に分析し、行政書士に依頼する場合とご自身で申請する場合のそれぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
帰化申請にかかる費用の全体像
帰化申請を検討する上で、まず気になるのが「費用」の問題です。費用は大きく分けて、ご自身で申請する場合にかかる「実費」と、行政書士に依頼する場合にかかる「専門家報酬」の2種類があります。
一見すると、自分で申請した方が安く済むように思えますが、実際には書類の取得費用や翻訳費用など、様々な実費が発生します。また、手続きにかかる時間や労力といった「見えないコスト」も無視できません。
ここでは、帰化申請にかかる費用の内訳を具体的に解説し、予算を立てる上での注意点を確認していきましょう。
自分で申請する場合にかかる「実費」の内訳
帰化申請そのものに、法務局へ支払う手数料は一切かかりません。しかし、申請に必要な書類を国内外から集める過程で、様々な費用が発生します。これらの実費は、申請者の国籍、家族構成、職業、来日からの経緯などによって大きく変動します。
- 本国の書類取得費用:出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書などを本国から取り寄せるための手数料や国際送料がかかります。国によっては数千円から数万円になることもあります。
- 日本の官公署で取得する書類の費用:住民票(1通300円程度)、戸籍謄本(1通450円程度)、課税証明書・納税証明書(1通300円程度)など、取得する市区町村によって手数料が異なります。家族全員分や過去数年分が必要になるため、合計すると数千円から1万円を超えることも珍しくありません。
- 翻訳費用:外国語で書かれた書類は、すべて日本語への翻訳が必要です。翻訳会社に依頼する場合、1枚あたり数千円から1万円程度が相場です。自分で翻訳することも可能ですが、その場合は翻訳者の署名・捺印が求められます。
- 交通費・通信費:法務局への相談や申請、書類取得のために役所へ足を運ぶ交通費、郵送でのやり取りにかかる切手代なども考慮しておく必要があります。法務局への相談は複数回に及ぶことが一般的です。
これらの実費を合計すると、一般的には数万円から、多い方では10万円以上になるケースもあります。
行政書士に依頼する場合の報酬相場
行政書士に帰化申請を依頼する場合、上記の実費に加えて「行政書士報酬」が発生します。この報酬は、事務所の方針やサポート内容の範囲によって大きく異なります。
一般的な相場としては、以下のようになっています。
- 会社員・個人事業主の方:15万円~25万円程度
- 会社経営者・役員の方:20万円~30万円程度
なぜ会社経営者の方が高くなる傾向にあるかというと、個人の書類に加えて、会社の登記事項証明書や決算報告書、法人事業税の納税証明書など、収集・作成すべき書類が格段に多くなり、手続きがより複雑になるためです。
また、家族(配偶者や子)が同時に申請する場合、1人追加あたり数万円の追加料金が設定されていることが一般的です。どこまでの業務を依頼するか(フルサポートか、書類チェックのみかなど)によっても料金は変動するため、契約前に必ず業務範囲と見積もりを確認することが重要です。
自分で帰化申請を行う場合のメリット・デメリット
費用を少しでも抑えたいという思いから、ご自身で帰化申請に挑戦しようと考える方は多いでしょう。
確かに、行政書士への報酬がかからない点は大きな魅力です。しかし、その裏には多くの時間と労力、そして精神的な負担が伴うことを理解しておく必要があります。ここでは、ご自身で申請を進めることの光と影、つまりメリットとデメリットを具体的に掘り下げていきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、本当に自分一人でやり遂げられるかを見極める判断材料にしてください。
メリット:費用を最大限に抑えられる
自分で申請する場合の最大のメリットは、やはり行政書士報酬がかからないという点に尽きます。
前述の通り、行政書士に依頼すれば十数万円から数十万円の費用が発生しますが、これを完全に節約できます。発生するのは書類取得などの実費のみとなるため、金銭的な負担を最小限に抑えたい方にとっては、非常に大きな魅力と言えるでしょう。
また、自ら手続きの全体像を学び、必要書類を一つひとつ集めていく過程で、日本の行政手続きに関する知識が深まるという副次的なメリットもあります。
デメリット:膨大な時間と労力、そして不許可のリスク
一方で、デメリットは多岐にわたります。特に以下の3点は、申請を断念する原因にもなりかねない重要なポイントです。
- 時間と労力の消費:帰化申請には、膨大な量の書類収集と作成が伴います。平日の昼間に何度も役所や法務局へ足を運ぶ必要があり、仕事をしている方にとっては大きな負担です。
法務局の相談予約は1ヶ月以上先になることも珍しくなく、書類の不備を指摘されれば、その都度やり直しとなります。申請準備から許可が下りるまで、トータルで1年以上の期間と、100時間以上の作業時間を要することも覚悟しなければなりません。
- 精神的なストレス:「この書類で本当に合っているのだろうか?」「翻訳はこれで大丈夫か?」といった不安が常につきまといます。
法務局の担当官からの厳しい指摘や、複雑な手続きの連続に、精神的に疲弊してしまう方も少なくありません。特に、本国の書類がなかなか手に入らない、家族の協力が得られないといった状況では、ストレスはさらに増大します。
- 不許可のリスク:最も避けたいのが、申請が不許可になってしまうことです。帰化申請は、書類を提出すれば必ず許可されるものではありません。書類の整合性が取れていなかったり、要件を満たしていることの立証が不十分だったりすると、不許可となる可能性があります。一度不許可になると、再申請は可能ですが、不許可の原因を解消しなければならず、さらに困難な道のりとなります。時間と労力をかけた結果が「不許可」では、目も当てられません。
行政書士に帰化申請を依頼するメリット・デメリット
専門家である行政書士に依頼することは、時間や労力を節約し、許可の可能性を高めるための有効な手段です。
しかし、当然ながら費用がかかるというデメリットも存在します。ここでは、ある会社員の方の実例を交えながら、行政書士に依頼することの具体的なメリットと、考慮すべきデメリットを詳しく解説します。このセクションを読むことで、行政書士への依頼がご自身にとって「価値ある投資」となるかどうかを判断できるでしょう。
メリット:時間・労力の節約と許可の確実性向上
行政書士に依頼するメリットは、単に「楽ができる」というだけではありません。
- 圧倒的な時間と労力の節約:行政書士は、申請に必要な書類を的確に判断し、効率的に収集します。依頼者は、行政書士の指示に従って最低限の書類(本人でなければ取得できないもの)を用意するだけで済み、平日に何度も役所や法務局へ行く必要がなくなります。
- 許可の可能性を最大限に高める:専門家は、帰化の要件を熟知しており、申請者一人ひとりの状況に合わせて、許可の可能性が最も高まるような書類構成を考えます。例えば、少し懸念材料(交通違反が多い、扶養家族が多いなど)がある場合でも、それを補うための説明資料や反省文を効果的に作成し、審査官に良い心証を与えるよう努めます。
- 精神的な安心感:手続きに関する一切の不安や疑問を、いつでも専門家に相談できます。「この場合はどうすれば?」という悩みを一人で抱え込む必要がなく、安心して結果を待つことができるのは、金銭には代えがたい大きなメリットです。
【エピソード:IT企業勤務 Aさんの場合】
毎日多忙なAさんは、自分で帰化申請を試みましたが、法務局への相談予約がなかなか取れず、ようやく取れた相談では書類の不備を大量に指摘され、心が折れかけていました。そこで当事務所にご依頼いただいた結果、書類収集や作成の大部分を任せることができ、本業に集中しながら申請準備を進めることができました。特に、複雑だった本国の親族関係を証明する書類の整理や、自身の収入の安定性をアピールする理由書の作成を代行したことで、スムーズに申請が受理され、無事に許可を得ることができました。「あのまま一人でやっていたら、途中で諦めていたかもしれません。専門家にお願いして本当に良かったです」とのお言葉をいただいています。
デメリット:費用の発生
行政書士に依頼する場合の唯一にして最大のデメリットは、報酬費用が発生することです。前述の通り、十数万円から数十万円の出費は、決して安い金額ではありません。
この費用を「安心と時間を買うための投資」と捉えられるかどうかが、依頼するか否かの大きな分かれ道となるでしょう。
ただし、多くの事務所では分割払いに対応しているため、一度に大きな金額を用意するのが難しい場合でも、相談してみる価値はあります。
行政書士選びで失敗しないための3つのポイント
「行政書士に依頼しよう」と決めたとしても、次に「どの行政書士に頼めばいいのか?」という問題に直面します。
行政書士と一言で言っても、その専門分野は様々です。建設業許可や相続を専門とする事務所もあれば、国際業務を専門とする事務所もあります。
帰化という人生の大きな決断を任せるパートナー選びは、絶対に失敗したくありません。ここでは、あなたにとって最適の行政書士を見つけるための、3つの重要なチェックポイントをご紹介します。
ポイント1:帰化申請の専門性と実績
まず最も重要なのが、帰化申請を専門的に取り扱っているか、そして十分な許可実績があるかという点です。
ホームページを見て、「帰化申請サポート」という記載があるだけでなく、具体的な許可事例やお客様の声が掲載されているかを確認しましょう。
帰化申請は、入管法だけでなく国籍法も関わる特殊な分野であり、最新の審査傾向を把握している専門家でなければ、適切なサポートは困難です。初回の相談時に、具体的な事例を交えて分かりやすく説明してくれるかどうかも、専門性を見極める良い指標となります。
ポイント2:明確な料金体系とサービス範囲
次に確認すべきは、料金体系です。「帰化申請一式〇〇円」と書かれていても、その料金にどこまでのサービスが含まれているのかを必ず事前に確認しましょう。
例えば、翻訳費用や書類取得の実費は別途必要なのか、万が一不許可になった場合の再申請に保証はあるのか、といった点です。後から「これも追加費用です」「それは業務範囲外です」といったトラブルにならないよう、契約前に書面で見積もりと業務範囲を明確に提示してくれる、誠実な事務所を選びましょう。
ポイント3:担当者との相性(コミュニケーションのしやすさ)
意外と見落としがちですが、担当してくれる行政書士との相性も非常に重要です。
帰化申請は、申請準備から許可まで1年以上の長い付き合いになります。その間、ご自身のプライベートな情報(家族関係、仕事、収入、時には過去の過ちなど)を包み隠さず話さなければなりません。そのため、「この人になら何でも話せる」と思えるような、
信頼できる人柄かどうかを見極めることが大切です。高圧的な態度を取らないか、こちらの話を親身に聞いてくれるか、専門用語ばかりでなく分かりやすい言葉で説明してくれるかなど、無料相談などを利用して、実際に話してみることを強くお勧めします。
まとめ
この記事では、帰化申請にかかる費用について、ご自身で申請する場合と行政書士に依頼する場合を比較しながら詳しく解説してきました。
ご自身で申請する場合、費用を最小限に抑えられるメリットがありますが、そのためには膨大な時間と労力、そして不許可になるリスクを覚悟する必要があります。一方、行政書士に依頼すれば費用はかかりますが、時間と労力を大幅に節約でき、専門家の知見によって許可の可能性を最大限に高めることができます。
どちらの選択が正しいということはありません。ご自身の日本語能力、法的な知識、仕事の状況、そして何よりも「時間」という有限な資源をどのように使いたいかを総合的に考慮して、最適な方法を選択することが重要です。
もし、少しでも手続きに不安を感じたり、専門家のサポートに価値を感じたりした場合は、一度、帰化申請を専門とする行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。あなたの長年の夢である「日本国籍の取得」を、確実なものにするための、最も賢明な一歩となるかもしれません。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、法務局への申請同行まで、お客様の帰化申請をトータルでサポートさせていただきます。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。豊富な経験と実績を持つ専門家が、あなたの状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルタント
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 

-
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 

-
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。


-
8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。


-
9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 

-
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る