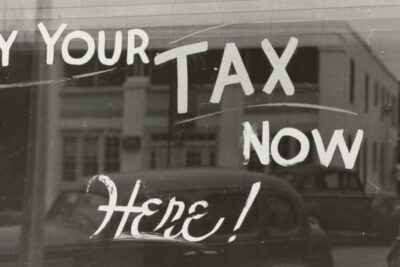帰化は取り消される?2024年入管法改正後の国籍剥奪リスクを専門家が解説
帰化申請サポート

日本での生活が長くなり、晴れて日本国籍を取得した方にとって、「一度許可された帰化が、後から取り消されることはあるのだろうか?」という不安は、決して他人事ではありません。
特に、2024年(令和6年)に成立・施行された改正入管法により、永住許可の取り消し要件が厳格化されたニュースは記憶に新しく、「帰化についても同じように厳しくなるのではないか」と心配される声も増えています。
苦労の末に手に入れた日本人としての地位が、将来的に揺らぐ可能性は本当にあるのでしょうか。こちらの記事では、帰化が取り消される可能性、その法的根拠、そして万が一の事態に備えるための具体的な対策について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
帰化の「取り消し」と「無効」の決定的違い
「帰化がなくなる」と一括りにされがちですが、法律の世界では「取り消し」と「無効」は全く異なる意味を持ちます。この違いを理解することは、ご自身の法的地位を正確に把握する上で非常に重要です。
「無効」とは、手続きにあまりにも重大かつ明白な欠陥があったために、最初から帰化許可そのものが存在しなかったと見なされるケースです。
一方で「取り消し」は、一度は有効に成立したものの、後から問題が発覚したためにその効力を将来に向かって失わせる処分を指します。まずは、この基本的な違いから見ていきましょう。
帰化が「無効」となる重大なケース
帰化が無効となるのは、極めて限定的な状況に限られます。これは、行政処分に「重大かつ明白な瑕疵(かし)」、つまり誰が見ても明らかな、致命的な誤りがある場合です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- すでに日本国籍を持っている人に対して、誤って帰化を許可してしまった。
- 本人に全く日本国籍を取得する意思がないにもかかわらず、手続きが進められ許可された。
- 申請者が亡くなっているにもかかわらず、死亡の事実を知らずに許可が出された。
- 15歳未満の子どもの申請が、親権者などの法定代理人ではない者によって行われた。
これらのケースでは、帰化許可は最初から効力がなかったことになり、戸籍が作成されていたとしても、その記載は遡って訂正されることになります。
「取り消し」と「無効」の比較表
両者の違いをより明確にするために、以下の表で比較してみましょう。特に「効力がいつ失われるか」という点が大きく異なります。
| 項目 | 取り消し | 無効 |
|---|---|---|
| 効力が失われるタイミング | 取り消された時点から将来に向かって失効 | 最初から効力がなかったことになる(遡及) |
| 原因 | 申請内容の虚偽など、一般的な瑕疵 | 重大かつ明白な瑕疵 |
| 影響の範囲 | 取り消しまでは有効な日本人として扱われる | 一度も日本人でなかったことになる |
このように、無効は非常に例外的であり、ほとんどの方に関係するのは「取り消し」の可能性です。次の章では、この「取り消し」についてさらに詳しく掘り下げていきます。
帰化が取り消される可能性と法的根拠
多くの方が最も知りたいのは、「実際に帰化が取り消されることはあるのか?」という点でしょう。結論から申し上げると、2024年現在、帰化許可が後から取り消されたという公式な事例は一件も報告されていません。
しかし、これは「将来も絶対に取り消されない」ことを保証するものではありません。法律の理論上は取り消しの可能性が存在しており、その背景を理解しておくことが重要です。なぜなら、万が一の事態に直面した際に、冷静に対応するための知識となるからです。
なぜ帰化の取り消しは一件も起きていないのか?
帰化の取り消しが極めて慎重に扱われるのには、いくつかの明確な理由があります。
第一に、無国籍者の発生を防ぐという国際的な要請です。日本の国籍法では二重国籍が原則として認められていないため、帰化する際には元の国籍を離脱することが求められます。もし安易に帰化を取り消してしまうと、その人はどの国にも属さない「無国籍者」となってしまい、著しい人権侵害につながる恐れがあります。これは国際法上の観点からも避けなければならない事態です。
第二に、社会的な影響の大きさです。帰化してから長い年月が経過している場合、その人の身分関係(結婚、親子関係など)や財産関係(不動産登記、会社役員など)は、日本人であることを前提に築かれています。帰化を取り消すことは、本人だけでなく、その家族や取引先など、社会全体に計り知れない混乱をもたらす可能性があります。
これらの理由から、法務省は帰化の取り消しに対して極めて抑制的な姿勢を取っているのです。
理論上の法的根拠と「虚偽申請」のリスク
では、なぜ「理論上は取り消し可能」と言われるのでしょうか。現在の国籍法には、帰化の取り消しを直接定めた条文はありません。しかし、帰化許可は法務大臣が行う「行政処分」の一種です。行政法の大原則として、重大な不正(例えば、申請内容に意図的な虚偽があった場合など)が後から発覚した場合には、その行政処分を取り消すことができると解釈されています。
実際に、過去の裁判で法務省は「詐欺の手段を用いて帰化の許可を得たような場合には、その許可を取り消すことも理論的には考えられる」との見解を示しています。
例えば、以下のようなケースが「虚偽申請」に該当する可能性があります。
- 重大な犯罪歴を隠して申請した。
- 婚姻関係が実態のない偽装結婚であったにもかかわらず、それを基に申請した。
- 納税や年金支払いについて、虚偽の証明書を提出した。
現時点で実例はないものの、このような悪質なケースでは、将来的に取り消しの対象となる可能性がゼロではない、と理解しておくべきでしょう。
2024年入管法改正が帰化に与える間接的な影響
2024年(令和6年)に施行された改正出入国管理及び難民認定法(入管法)は、主に「永住者」の在留資格取り消し事由を厳格化したものです。この法改正が、直接「帰化」の取り消しルールを変更するものではありません。しかし、この流れが帰化申請の審査や将来の法改正に全く影響しないと考えるのは早計です。
この法改正は、日本政府が在留外国人のコンプライアンス(法令遵守)をより重視する姿勢を明確に示したものと捉えることができます。永住許可という安定した在留資格ですら、公的義務の不履行によって取り消され得る時代になったのです。
厳格化された永住許可の取り消し事由
今回の改正で、永住許可の取り消し事由として新たに追加・明確化されたのは、主に以下の点です。
- 意図的な公租公課(税金や社会保険料)の不払い:単なる払い忘れではなく、意図的に支払いを怠った場合に、永住許可が取り消される可能性があります。
- 一定の法律違反:在留カードの常時携帯義務など、入管法に定められた義務に違反した場合や、窃盗罪・詐欺罪などで懲役・禁錮刑に処せられた場合も対象となります。
これまで永住許可は一度取得すれば非常に安定した資格とされてきましたが、今後は納税や社会保険料の支払いをはじめとする公的義務を誠実に履行し続けることが、これまで以上に強く求められることになります。
帰化申請における審査基準への波及
この永住許可の厳格化は、帰化申請の審査にも間接的な影響を与える可能性があります。
帰化の要件の一つに「素行が善良であること(素行要件)」があります。この要件の判断において、納税や年金、健康保険料などの公的義務の履行状況が、これまで以上に厳しくチェックされることが予想されます。
例えば、過去に税金の滞納があった場合、これまではその理由や現在の納付状況を丁寧に説明することで許可されるケースも多くありました。しかし今後は、「なぜ滞納したのか」「再発防止策は何か」といった点について、より説得力のある説明が求められるようになるでしょう。
法改正の直接の対象ではないからと安心するのではなく、「日本人になるということは、公的義務を誠実に果たす覚悟が問われる」という社会的なメッセージとして受け止め、申請準備段階から襟を正す必要があると言えます。
帰化後の国籍を維持するための具体的な注意点
前述の通り、帰化が取り消される可能性は極めて低いのが現状です。しかし、その低い可能性すらもゼロにし、安心して日本での生活を送るためには、帰化申請時と帰化後の両方で注意すべき点があります。
特に重要なのは、「誠実さ」です。申請書類に嘘偽りを書かないことはもちろん、日本人となった後も、社会の一員としての責任を果たし続ける姿勢が何よりも大切です。ここでは、具体的な注意点をリストアップして解説します。
帰化申請時に絶対に守るべきこと
帰化申請は、あなたの過去から現在までを正直に申告する手続きです。ここで不正を行うことは、将来に禍根を残す最も危険な行為です。
- 虚偽の記載は絶対にしない:収入や職歴、家族関係、犯罪歴など、いかなる項目においても事実と異なる記載をしてはいけません。不利な情報であっても正直に申告し、その背景を説明することが重要です。
- 証明書類の偽造・変造は行わない:納税証明書や給与明細などを改ざんする行為は、発覚すれば一発で不許可になるだけでなく、将来的な取り消し理由にもなり得ます。
- 面接では誠実に対応する:申請後の法務局での面接では、審査官の質問に対して正直かつ丁寧に回答しましょう。不明な点や記憶が曖昧な点を、その場しのぎでごまかすのは避けるべきです。
審査官は、あなたが日本人としてふさわしい誠実な人物かどうかを見ています。完璧な経歴よりも、正直な姿勢の方が高く評価されることを覚えておきましょう。
帰化後に日本人として果たすべき義務
無事に帰化が許可され、日本人になった後も、社会の一員としての責任は続きます。むしろ、ここからが本番です。
- 法令遵守の徹底:交通違反や税金の滞納、社会保険料の未納など、法律で定められたルールはきちんと守りましょう。特に、改正入管法で永住許可の取り消し事由となった公租公課の支払いは、日本人としても当然の義務です。
- 各種届出義務の履行:住所を変更した際の住民票の異動届や、結婚・離婚・出生・死亡など身分関係に変動があった際の戸籍の届出は、定められた期間内に必ず行いましょう。
- 重要書類の保管:「帰化許可証書」や帰化後の最初の戸籍謄本、官報の写しなど、帰化に関する書類は大切に保管しておきましょう。万が一、将来何らかの確認が必要になった際に、あなたが正当な手続きを経て日本人になったことを証明する重要な証拠となります。
これらの義務を誠実に果たし続けることが、あなたの日本国籍を盤石なものにする最善の方法です。
まとめ
この記事では、帰化の取り消しに関する法的根拠や実情、そして2024年の入管法改正が与える影響について解説してきました。
結論として、帰化が後から取り消される可能性は、現時点では極めて低いと言えます。その背景には、無国籍者の発生防止という国際的な要請や、社会的な影響の大きさへの配慮があります。
しかし、理論上の取り消し可能性は存在しており、特に「虚偽の申請」は将来的なリスクとなり得ます。また、永住許可の取り消し要件が厳格化された近年の流れは、帰化申請の審査においても、納税や社会保険料の支払いといった公的義務の遵守がより一層重視されることを示唆しています。
最も重要なのは、帰化申請の段階で正直かつ誠実な手続きを貫き、日本人となった後も、社会の一員としての責任を果たし続けることです。それが、あなたの日本での未来を最も確かなものにする道筋です。
帰化申請に関するご不安や、ご自身の状況で注意すべき点など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ一度、経験豊富な行政書士にご相談ください。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルタント
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 

-
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 

-
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。


-
8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。


-
9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 

-
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る