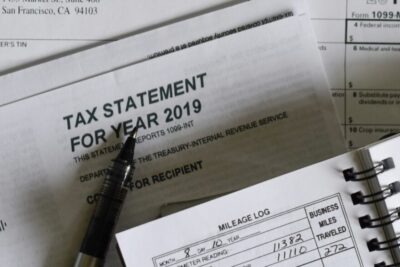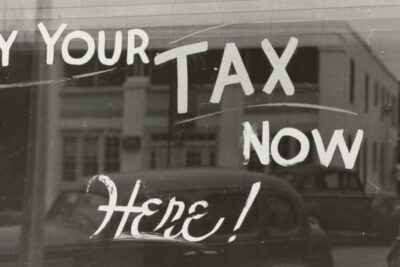帰化申請の面接を徹底解説!質問内容から当日の注意点まで
帰化申請サポート

帰化申請という大きな決断をし、膨大な書類を準備して法務局に受理された後、多くの方が次に迎えるのが「面接」というステップです。
「面接では一体何を聞かれるのだろう?」「厳しい雰囲気なのだろうか?」「もしうまく答えられなかったらどうしよう?」といった不安や疑問を抱えている方も少なくないでしょう。
この面接は、提出した書類の真実性を確認し、申請者ご本人の帰化に対する意思や日本社会への定着性を判断するための非常に重要な手続きです。準備を怠ると、思わぬところで審査に影響が出てしまう可能性もゼロではありません。
こちらの記事では、帰化申請の面接で実際にどのようなことが聞かれ、どのような準備をすれば良いのか、当日の流れから注意点まで詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
帰化申請の面接とは?その目的と重要性
帰化申請の面接は、単なる形式的な手続きではありません。法務局の担当官が、申請者と直接対話することで、書類だけでは分からない人柄や日本語能力、そして日本国民となるにふさわしい人物かどうかを総合的に判断するための重要な機会です。この面接を通じて、申請内容に虚偽がないか、帰化の意思は固いか、そして日本社会で安定して生活していけるかどうかが確認されます。面接の結果は、帰化の許可・不許可を決定する上で大きなウェイトを占めるため、誠実な態度で臨むことが何よりも大切です。
面接の呼び出し時期と場所
帰化申請の書類が法務局に受理されてから、おおむね2ヶ月から4ヶ月後に、担当官から電話で面接の日程調整の連絡が入るのが一般的です。ただし、これはあくまで目安であり、申請した法務局の混雑状況や申請者の状況によって、1ヶ月程度で連絡が来ることもあれば、半年近く待つケースもあります。連絡があった際には、提示された日程で都合が悪い場合は正直に伝え、再調整をお願いしましょう。面接場所は、原則として申請書類を提出した法務局・地方法務局の国籍課で行われます。
面接の目的:書類の真実性と人物像の確認
面接の最大の目的は、提出された膨大な申請書類の内容が事実と相違ないかを確認することです。担当官は、申請書類を熟読した上で、内容の整合性や不明瞭な点について質問をします。例えば、職歴や居住歴、家族関係、収入や納税状況など、書類に記載した内容について、より深く掘り下げて尋ねられます。また、同時に申請者の日本語能力もチェックされます。難しい法律用語を理解する必要はありませんが、小学校3年生程度の日本語で、担当官の質問を理解し、自分の言葉で回答できる能力が求められます。
面接時間はどのくらい?
面接時間は申請者の状況によって大きく異なりますが、平均的には30分から1時間程度です。ただし、家族構成が複雑であったり、転職回数が多かったり、過去に交通違反や何らかのトラブルがあったりするなど、担当官が確認すべき事項が多い場合は、1時間半から2時間以上に及ぶこともあります。面接当日は、時間に余裕を持ったスケジュールを組んでおくことをお勧めします。もし面接が長引いたとしても、それは担当官があなたのことをより深く理解しようとしている証拠ですので、焦らず落ち着いて対応しましょう。
【完全ガイド】帰化申請の面接で聞かれる具体的な質問内容
面接で何を聞かれるのか、事前に知っておくだけで心の準備ができます。質問内容は申請者一人ひとりの状況に応じて異なりますが、基本的には提出した「履歴書」や「動機書」に沿って進められます。ここでは、多くの申請者が実際に質問されている項目をカテゴリー別に分け、具体的な質問例とともに詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、どのように答えるかシミュレーションしてみましょう。
① これまでの経緯(来日、学歴、職歴)について
あなた自身がどのような人生を歩んできたのか、その人となりを知るための質問です。特に、日本に来た理由や、これまでの生活について具体的に聞かれます。
- なぜ日本に来ようと思ったのですか?(来日の動機)
- 初めて日本に来た時の印象はどうでしたか?
- これまでの在留資格の遍歴を教えてください。
- 学校(小学校から最終学歴まで)での思い出や、得意だった科目は何ですか?
- アルバイトの経験はありますか?どのような仕事内容でしたか?
- これまでで一番長く勤めた会社について教えてください。(仕事内容、役職、やりがいなど)
- 転職回数が多いようですが、それぞれの理由は何ですか?
② 家族・親族・交友関係について
家族は、申請者の生活の基盤であり、帰化後の生活の安定性を判断する上で重要な要素です。配偶者や子供、両親、兄弟姉妹について詳しく質問されます。
- 配偶者とはどこで、どのように出会いましたか?交際期間はどのくらいですか?
- (配偶者が外国人の場合)配偶者も帰化を考えていますか?
- ご両親はあなたの帰化について何と言っていますか?賛成していますか?
- 日本や母国にいるご兄弟とは、どのくらいの頻度で連絡を取っていますか?
- お子さんの学校での様子はどうですか?日本の生活に馴染んでいますか?
- 親しい友人はいますか?(日本人、外国人問わず)休日はどのように過ごしていますか?
③ 仕事と収入(生計)について
日本で独立して安定した生活を送れるかどうか、という「生計要件」を確認するための重要な質問です。現在の仕事内容や収入、今後の見通しについて具体的に回答する必要があります。
- 現在の会社での具体的な仕事内容を教えてください。
- 毎月の手取り収入はどのくらいですか?ボーナスはありますか?
- その収入で、ご家族の生活は安定していますか?
- 今後、転職や独立を考えていますか?
- (自営業者の場合)事業内容や取引先、売上や経費について詳しく教えてください。
④ 納税・年金・健康保険の支払い状況について
納税や社会保険料の支払いは、日本国民としての三大義務の一つであり、これをきちんと果たしているかは「素行要件」の根幹をなす部分です。未納や滞納があると、帰化は極めて難しくなります。
- 住民税や所得税は、きちんと納めていますか?
- これまで税金の支払いが遅れたことはありませんか?
- 国民年金や厚生年金には加入していますか?保険料は毎月支払っていますか?
- 過去に年金を支払っていなかった期間はありますか?それはなぜですか?
- 健康保険の種類(国民健康保険、会社の社会保険など)と、保険料の支払い状況を教えてください。
⑤ 遵法精神(交通違反・犯罪歴)について
日本の法律を守って生活しているかどうかも「素行要件」の重要な判断材料です。たとえ軽い交通違反であっても、正直に申告することが求められます。隠し事をすると、かえって心証を悪くする可能性があります。
- これまでに交通違反(駐車違反、スピード違反など)をしたことはありますか?それはいつ、どのような違反でしたか?
- (違反歴がある場合)その時の状況と、現在どのように反省しているか教えてください。
- 過去に警察にお世話になったこと(逮捕歴など)はありますか?
- オーバーステイや不法就労の経験はありますか?
面接当日の流れと心構え|服装や持ち物、注意点
面接当日は誰でも緊張するものです。しかし、事前に流れや注意点を把握しておけば、落ち着いて臨むことができます。ここでは、面接当日の具体的な流れから、服装や持ち物、そして面接官に良い印象を与えるための心構えまでを詳しく解説します。万全の準備で、自信を持って面接に臨みましょう。
面接当日の服装と持ち物
服装に厳格な決まりはありませんが、清潔感のある、きちんとした服装を心がけましょう。男性であればスーツまたはジャケットに襟付きのシャツ、女性であればスーツやワンピース、きれいめのブラウスにスカートやパンツといったスタイルが無難です。Tシャツやサンダル、ダメージジーンズなどのラフすぎる格好は避けましょう。
持ち物については、法務局から特に指定がない場合でも、以下のものは持参すると安心です。
- 在留カード(または、特別永住者証明書)
- 運転免許証(お持ちの方)
- 健康保険証
面接の心構え:「正直」と「誠実」が鍵
面接で最も大切なことは、嘘をつかず、正直に、誠実な態度で回答することです。担当官は、日々多くの申請者と接しているプロです。曖昧な回答や嘘はすぐに見抜かれてしまいます。もし自分にとって不利な事実(例えば、過去の交通違反や税金の支払い遅延など)があったとしても、正直に話し、深く反省している態度を示すことが重要です。隠し事をしたり、嘘をついたりすることは、信頼を失い、帰化が不許可となる最大の原因になりかねません。
また、担当官の質問の意図が分からない場合や、言葉が聞き取れなかった場合は、遠慮せずに「申し訳ありません、もう一度お願いします」と聞き返しましょう。分かったふりをして見当違いの回答をする方が問題です。ハキハキとした声で、担当官の目を見て話すことを心がけてください。
面接に関するよくある質問(FAQ)
帰化申請の面接に関して、多くの方が抱く共通の疑問があります。例えば、「家族も一緒に面接を受けるの?」「行政書士は同席できるの?」といった質問です。ここでは、そうしたよくある質問とその回答をまとめました。ご自身の疑問と重なる点がないか、ぜひチェックしてみてください。
Q1. 家族(配偶者や子供)も一緒に面接を受けますか?
A1. 申請者本人(15歳以上)が面接の対象となります。ただし、配偶者や生計を同一にする親族が一緒に帰化申請をしている場合は、同日に家族全員で面接を行うことが一般的です。また、申請者本人が日本語でのコミュニケーションに不安がある場合や、結婚の実態を確認する必要がある場合など、担当官が必要と判断すれば、日本人配偶者や婚約者が同席を求められることもあります。15歳未満のお子様については、通常、面接はありませんが、簡単な質問をされるケースもあります。
Q2. 申請を依頼した行政書士は面接に同席できますか?
A2. いいえ、できません。帰化の面接は、申請者本人の意思や人物像を確認する場であるため、行政書士といえども代理人として面接に同席することは認められていません。申請者ご本人のみで面接に臨む必要があります。ただし、信頼できる行政書士であれば、想定される質問への回答の準備や、面接シミュレーションなど、万全のサポートを提供してくれます。事前にしっかりと打ち合わせを行い、不安を解消しておくことが大切です。
Q3. 日本語能力テストはありますか?どのくらいのレベルが必要ですか?
A3. 面接とは別に、筆記形式の「日本語能力テスト」が実施されることがあります。これは全ての申請者に対して行われるわけではなく、担当官が面接でのやり取りの中で「もう少し日本語能力を確認する必要がある」と判断した場合に実施されます。テストの内容は、小学校3年生程度のひらがな、カタカナ、漢字の読み書きができるレベルです。自分の名前や住所、簡単な文章の読み書きができれば問題ありません。日頃から日本のニュースを見たり、新聞を読んだりして、日本語に触れる機会を増やしておくと良いでしょう。
まとめ
この記事では、帰化申請における面接について、その目的から具体的な質問内容、当日の心構えまでを詳しく解説しました。面接は、あなたの日本への想いを直接伝えることができる貴重な機会です。ポイントを再確認しておきましょう。
- ✔ 面接は申請書類の真実性を確認し、申請者の人柄を判断するために必ず実施されます。
- ✔ 質問は提出書類に基づいて行われるため、申請前に控えをコピーし、内容を熟読しておくことが重要です。
- ✔ 面接での最大のポイントは、「嘘をつかず、正直に、誠実な態度で」回答することです。不利な事実も隠さず話しましょう。
- ✔ 面接には行政書士などの代理人は同席できず、申請者本人のみで臨む必要があります。
- ✔ 服装は清潔感のあるものを、持ち物は在留カードやパスポート、申請書類の控えを忘れずに持参しましょう。
面接は決してあなたを落とすための試験ではありません。担当官は、あなたのことを理解しようと努めています。この記事を参考にしっかりと準備を行い、自信を持ってあなたの言葉で、日本国民になりたいという熱意を伝えてください。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。帰化申請は、人生における大きな一歩です。膨大で複雑な書類準備、法務局との折衝、そして面接対策まで、専門家がトータルでサポートすることで、お客様の不安を解消し、許可取得の可能性を最大限に高めます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 

-
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 

-
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。


-
8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。


-
9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 

-
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る