帰化後の戸籍:新制度とフリガナ記載義務化で何が変わる?
帰化申請サポート

日本での生活が長くなり、「日本人として、この国で生きていきたい」と考えるようになったとき、多くの方が「帰化申請」を検討します。しかし、帰化への道は決して平坦ではありません。
特に、日本国籍を取得した後に新たに編製される「戸籍」については、その役割や記載内容、そして最新の法改正による変更点など、知っておくべき重要な情報が数多く存在します。ご自身で申請準備を進める中で、「帰化後の戸籍ってどうなるの?」「フリガナ記載義務化って何?」といった疑問や不安を抱える方は少なくありません。これらの疑問を解消し、安心して日本での新たな生活をスタートできるよう、こちらの記事では、帰化後の戸籍に関する最新情報と、新制度における注意点について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
帰化許可から戸籍に記載されるまでの流れと最新の変更点

帰化が許可され、日本国籍を取得した後の手続きは、新たな日本人としての第一歩を踏み出す上で非常に重要です。特に、戸籍の編製は、これまでの外国籍から日本国籍への移行を公的に証明する最終段階となります。このプロセスには、いくつかの重要なステップがあり、近年では法改正によって新たな変更点も加わりました。ここでは、帰化許可後の具体的な流れと、特に注目すべき最新の変更点について詳しく解説していきます。
帰化届の提出と戸籍の編製
帰化が官報に告示された日から1ヶ月以内に、住所地を管轄する市町村役場、または任意に定めた本籍地を管轄する市町村役場へ「帰化届」を提出します。この届出が受理されると、自動的に新たな戸籍が編製され、約1週間から10日程度で戸籍謄本などの取得が可能になります。この戸籍には、あなたの氏名、生年月日、そして帰化の事実などが記載され、日本人としての身分関係が公的に証明されることになります。
官報の電子化とプライバシー保護の強化(令和7年4月1日施行)
これまで、帰化許可者の情報は官報に掲載され、その住所が詳細に記載されていました。しかし、令和7年4月1日からは「官報の発行に関する法律」の施行により、官報が電子化され、帰化許可者の告示内容が大きく変更されました。これにより、個人のプライバシー保護が強化されることになります。
具体的には、官報に記載される住所は、これまでの詳細な番地までではなく、市町村名まで(政令指定都市および東京都の特別区においては区まで)に限定されます。また、帰化許可者の官報掲載記事の公開期間も、90日間に限定されることになりました。これは、有名人の方々を含め、帰化によって住所が公になってしまうという長年の課題に対する、時代の流れに沿った改善と言えるでしょう。
戸籍のフリガナ記載義務化(令和7年5月26日施行)
もう一つの大きな変更点は、令和7年5月26日から施行される戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになることです。これまで、氏名のフリガナは住民基本台帳などには登録されていましたが、戸籍上は公証されていませんでした。この改正により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加され、より正確な身分情報の管理が可能となります。
この変更は、帰化申請にも影響を与えます。これまでは帰化後の氏名にフリガナの記載は必須ではありませんでしたが、今後は帰化申請書にもフリガナの記載が必要となります。もし、改正法施行前に帰化申請中の方で、申請書にフリガナを記載していない場合は、法務局からフリガナを確認するための連絡が来る可能性がありますので、注意が必要です。
戸籍の役割と記載内容:なぜ重要なのか
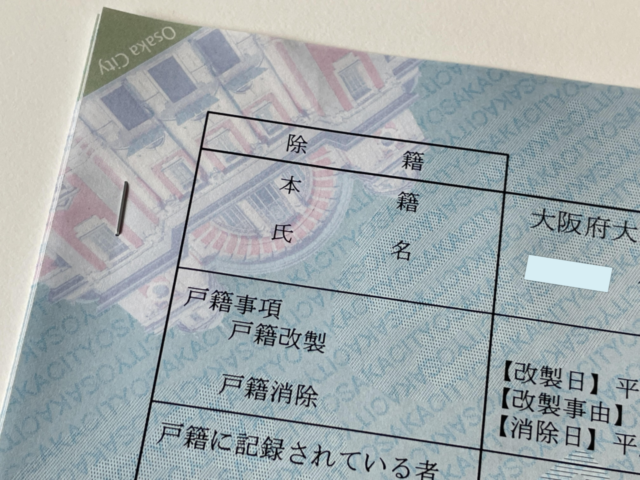
戸籍は、日本において個人の身分関係を公的に証明する唯一の公文書であり、その役割は多岐にわたります。帰化によって新たに戸籍が編製されるということは、あなたが日本人として、この国の社会システムの中に組み込まれることを意味します。では、具体的に戸籍はどのような役割を担い、どのような情報が記載されているのでしょうか。ここでは、戸籍の持つ本質的な意味とその重要性について深く掘り下げていきます。
戸籍の3つの主要な役割
戸籍には、主に以下の3つの重要な役割があると言われています。
- 家族関係を明らかにすること: 誰が誰の親で、誰が誰の子であるかといった血縁関係や、夫婦関係などを公的に記録します。
- 身分関係を明らかにすること: 出生、婚姻、離婚、死亡といった個人の重要な身分変動を時間的序列にしたがって記録し、公証します。
- 日本人であることを明らかにすること: 日本国籍を持つ者であることを証明する唯一の公文書であり、外国籍の方には戸籍がありません。
戸籍は正式には「戸籍全部事項証明書」という名称で、その人の親は誰で、いつどこで生まれて、独身もしくは既婚で、子どもは誰で、日本人である、というような身分関係を時間的序列にしたがって記録し、公証する唯一の公文書というわけです。これは、あなたの人生の重要な節目を公的に記録し、証明する「人生の履歴書」とも言えるでしょう。
戸籍に記載される具体的な情報
戸籍には、個人の身分関係に関する様々な情報が詳細に記載されます。基本的な記載事項は以下の通りです。
- 氏名(フリガナを含む)
- 出生の年月日
- 戸籍に入った原因及び年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫又は妻である旨
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
- その他法務省令で定める事項
そして、帰化によって初めて戸籍が編製される場合には、上記に加えて以下の事項が記載されます。これらの情報は、あなたが外国籍から日本国籍を取得した経緯を公的に記録するものです。
- 帰化日
- 帰化前の国籍
- 帰化前の氏名
戸籍が必要となる具体的な場面
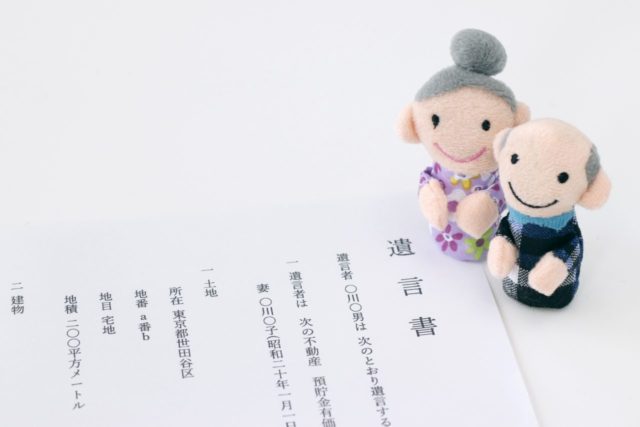
戸籍は、普段の生活の中で意識することは少ないかもしれませんが、人生の重要な節目や公的な手続きにおいて、その提出を求められる場面が数多く存在します。帰化によって新たに戸籍が編製されたあなたは、今後、日本人として様々な手続きを行う際に、この戸籍が必要となることを理解しておく必要があります。ここでは、具体的にどのような場面で戸籍が必要になるのか、代表的なケースを詳しく見ていきましょう。
日常生活で戸籍が必要になる主なケース
戸籍が必要となる代表的な場面は以下の通りです。
- 公正証書遺言を作成するとき
- 相続手続を行うとき
- 保険金の請求をするとき
- パスポートの申請をするとき
- 婚姻届を提出するとき
- 年金の請求をするとき
各ケースの詳細
公正証書遺言を作成するとき
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、公証役場で作成する公正証書遺言の場合、戸籍の提出が求められます。これは、公証人が遺言者の家族関係を確認し、相続人となる人を正確に特定するために必要となるためです。場合によっては、親の出生が記載されている戸籍まで遡って入手する必要があることもあります。
相続手続を行うとき
故人の財産を相続する際には、不動産の名義変更や預貯金の名義変更など、様々な相続手続きが必要となります。これらの手続きを行う際、法務局や金融機関は、故人と相続人の関係を公的に証明するために戸籍の提出を求めます。戸籍によって、法定相続人が誰であるかを明確に示すことができるため、非常に重要な書類となります。
保険金の請求をするとき
死亡保険金などの保険金を請求する際にも、戸籍の提出が必要となります。保険会社は、戸籍を通じて故人(被保険者)と保険金受取人の関係を確認し、正当な受取人であることを確認します。これにより、保険金の不正請求を防ぎ、適正な支払いを保証します。
パスポートの申請をするとき
海外渡航に必要なパスポート(旅券)を申請・更新する際にも、戸籍謄本または抄本の提出が義務付けられています。戸籍は、申請者が日本国籍を持つ者であることを公的に証明する唯一の書類であり、日本のパスポートを取得するために不可欠です。
婚姻届を提出するとき
結婚して「婚姻届」を提出する際にも、戸籍の提出が必要となります。ただし、婚姻届の提出先が本籍地を管轄する市町村役場である場合は、戸籍の提出は不要です。結婚により新たに夫婦の戸籍が編製されることになりますが、この戸籍には二人の家族関係や身分関係が記載されるため、従前の戸籍でこれらの情報を確認する必要があるのです。
ちなみに、片方が外国籍の方と結婚する場合、日本人が筆頭者として戸籍が編製され、外国籍の配偶者については氏名、生年月日、国籍のみが記載されることになります。
年金の請求をするとき
老齢年金や遺族年金など、各種年金を請求する際にも、請求者の身分関係を明らかにするために戸籍の提出が必要となる場合があります。年金事務所は、戸籍を通じて請求資格の有無や受給順位などを確認し、適正な年金給付を行います。
帰化の事実を戸籍から分かりにくくする方法

帰化によって日本国籍を取得したものの、過去の経緯を戸籍から完全に消したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。特に、結婚などの際に配偶者に戸籍を見られることで、帰化の事実を知られることを避けたいと考えるケースもあるでしょう。残念ながら、戸籍から帰化に関する事項を完全に抹消することはできません。しかし、一見しただけでは帰化の事実が分かりにくくする方法は存在します。ここでは、その具体的な方法について解説します。
帰化の事実を分かりにくくする2つの方法
戸籍から帰化に関する事項を完全に消すことはできませんが、以下の方法で一見しただけでは分かりにくくすることが可能です。
- 転籍する
- 戸籍の改製
転籍による方法
「転籍」とは、本籍地を別の市町村に移す手続きのことです。転籍を行うと、新しい本籍地で新たな戸籍が編製されます。この新しい戸籍には、帰化に関する事項は記載されません。そのため、この新しい戸籍を一見しただけでは、あなたが帰化したという事実は分からないということになります。
ただし、注意点があります。新しい戸籍には、あなたの実父母の氏名が記載されます。もし、父母が外国籍のままであなただけが帰化した場合、父母の氏名は本名そのままが記載されます。この点から、完全に過去を隠せるわけではないことを理解しておく必要があります。
また、「一見しただけでは分からない」というのは、あくまで新しい戸籍を見た場合の話です。相続手続きなどの特定の目的で戸籍を遡って収集する場合には、帰化当時の戸籍にたどり着くことになり、それを見れば帰化の事実が分かってしまいます。しかし、一般的に他人の戸籍を遡って取得することは、行政書士のような士業の者が業務上行う場合などを除き、非常に限定的です。そのため、過度に心配する必要はないかもしれません。
戸籍の改製による方法
「戸籍の改製」とは、法改正によって戸籍の様式が変更され、それに伴い戸籍が編製し直されることを指します。近年では、平成6年に戸籍の様式が見直され、縦書きから横書きに変更されるという大きな改製がありました。この改製が行われると、旧戸籍に記載されていた帰化に関する事項は、新しい戸籍には移記されません。
しかし、戸籍の改製は個人の意思で自由にできるものではなく、国の法改正によって行われるものです。そのため、この方法を意図的に利用することはできませんが、もし将来的に戸籍の改製が行われた場合には、帰化の事実がより分かりにくくなる可能性があるということを、参考程度に知っておくと良いでしょう。ちなみに、これまでに戸籍の改製は、戦前に4回、戦後に2回行われています。
まとめ
本記事では、帰化後の戸籍について、その編製から役割、必要となる場面、そして最新の法改正による変更点まで、幅広く解説してまいりました。帰化によって日本国籍を取得することは、新たな人生のスタートであり、それに伴い「戸籍」という重要な公文書があなたのために編製されます。この戸籍が、日本人としてのあなたの身分関係を公的に証明し、様々な手続きの基盤となることをご理解いただけたかと思います。
特に、令和7年4月1日からの官報の電子化とプライバシー保護の強化、そして令和7年5月26日からの戸籍のフリガナ記載義務化は、帰化申請を検討されている方や、すでに帰化された方にとっても非常に重要な変更点です。これらの最新情報を踏まえ、安心して日本での生活を送るための一助となれば幸いです。
また、帰化の事実を戸籍から完全に消すことはできませんが、転籍や戸籍の改製といった方法で、一見しただけでは分かりにくくすることも可能です。ご自身の状況に合わせて、適切な対応を検討されることをお勧めします。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、法務局での申請までサポートさせていただきます。帰化申請は、多くの書類準備と複雑な手続きを伴います。最新の法改正にも対応し、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供することで、スムーズな帰化申請を強力にバックアップいたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 

-
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 

-
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。


-
8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。


-
9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 

-
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る











