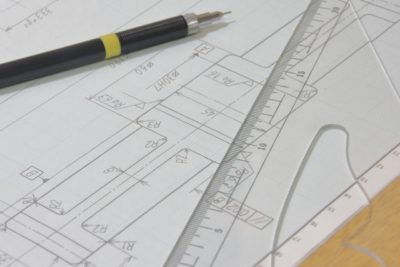外国人が知るべき就労ビザの取得方法とは?企業カテゴリーや申請方法まで詳しく解説
ビザ(在留資格)申請サポート

日本で働くことを希望する外国人にとって、就労ビザの取得は必要不可欠な手続きです。2024年には出入国在留管理庁による制度改正や新たなガイドラインの導入により、申請プロセスにも変化が見られています。
本記事では、就労ビザの基本的な仕組みから具体的な取得方法、さらには失敗事例と対策まで、最新の情報を基に包括的に解説します。
これから日本での就職を目指す外国人の方、外国人採用を検討している企業の方にとって、実務的で役立つ情報をお届けいたします。
― 目次 ―
就労ビザとは?
就労ビザとは、外国人が日本国内で合法的に就労するために必要な査証のことです。
厳密には、「ビザ」は海外の日本領事館等で発行される入国許可証であり、日本国内での活動許可は「在留資格」と呼ばれます。
一般的に「就労ビザ」と呼ばれているのは、就労が認められる在留資格を指しています。
重要な区別
- ビザ(査証):海外の日本領事館で発行される入国許可証
- 在留資格:日本国内での活動を許可する資格(在留カードに記載)
在留資格との関係性
日本の出入国在留管理制度では、在留資格は29種類に分類されており、このうち就労が認められるものは約19種類あります。
2025年現在、最も多く利用されているのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。
在留資格の種類に関しては下記記事をご覧ください。
【完全ガイド】在留資格29種類を徹底解説!取得方法や就労可否も紹介
就労ビザの種類と特徴
| 在留資格 | 対象業務 | 在留期間 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング等 | 5年、3年、1年、3月 | 大学卒業または実務経験10年 |
| 企業内転勤 | 海外支社からの転勤者 | 5年、3年、1年、3月 | 転勤前1年以上の勤務実績 |
| 高度専門職 | 高度人材(研究、技術、経営) | 5年(1号)、無期限(2号) | ポイント制70点以上 |
| 特定技能 | 12分野の特定産業 | 1号:通算5年、2号:3年等 | 技能試験合格または技能実習修了 |

就労ビザの取得要件
就労ビザの取得には、以下の基本要件を満たす必要があります。
- 学歴要件:大学卒業以上(技術・人文知識・国際業務の場合)
- 職歴要件:関連業務での実務経験(学歴不足の場合は10年以上)
- 職務内容の適合性:学歴・職歴と従事予定業務の関連性
- 報酬の適正性:日本人と同等以上の報酬
- 雇用先の安定性:受入機関の経営状況
職業ごとの特有の要件
1.技術系職種
- 理工系大学卒業または情報処理技術者試験合格
- システムエンジニア、プログラマー、機械設計者など
2.人文系職種
- 人文科学系大学卒業(経済、法律、社会学など)
- 営業、経理、総務、マーケティングなど
3.国際業務
- 外国の文化的背景を活かした業務
- 通訳・翻訳、語学教師、海外取引業務など
企業カテゴリー制(カテゴリー1-4)の詳細解説
就労ビザ(在留資格)の申請において、外国人を雇用する企業(所属機関)は、その規模や公的な信頼度によって4つのカテゴリーに分類されます。この分類は、提出書類の簡素化、審査期間の目安、そして在留期間の決定に大きく影響します。
カテゴリー分類の基準
企業カテゴリーは、売上高や従業員数といった一般的な企業規模の指標ではなく、公的な情報や税務上の実績に基づいて判断されます。
具体的には、以下の3つの要素が主な判断基準となります。
- 株式の上場状況や公的機関であるか否か
- 前年度の源泉徴収税額
- 前年度の法定調書合計表を提出しているか
カテゴリー1
上場企業や国・地方公共団体、独立行政法人など信頼性が非常に高いと認められる機関が該当します。
提出書類の大幅な簡素化がされ、雇用企業の事業内容や経営状況を証明する書類(会社案内、決算書、法定調書など)の提出が原則として免除されます。
また、経営の安定性がすでに証明されているため、審査がスムーズに進む傾向があり、比較的短期間でも結果が出やすくなっています。
初回申請でも、最長の「5年」の在留期間が許可されるケースが多いです。
カテゴリー2
源泉徴収税額1,000万円以上の期間で、中堅・優良企業が主に該当します。
具体的には、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に記載された「源泉徴収税額」が1,000万円以上の団体・または個人で、在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている機関になります。
カテゴリー1ほどではありませんが、提出書類は簡素化され、雇用企業の経営状況を証明する複数の書類(決算書類など)が免除されることがあります。
審査の期間もカテゴリー1同様比較的短く、在留期間は3年または5年での許可が多いです。
カテゴリー3
カテゴリー2の要件を満たさないものの、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している機関が該当します。
具体的には、中小企業や小規模な事業所が多く含まれます。
会社の登記事項証明書、決算報告書の写し、事業内容がわかる資料、「法定調書合計表」の写しなどが必要で、カテゴリー1・2に比べると提出書類は多くなります。
書類が増える分、審査にも時間が掛かる傾向にあります。
また、初回申請では「1年」の在留期間が許可されることが多いです。
カテゴリー4
カテゴリー1から3のいずれにも該当しない機関が該当します。
具体的には、設立1年未満の新設法人や、法定調書合計表をまだ提出していない企業などが含まれます。
最も多くの提出書類を求められ、上記カテゴリー3の書類に加え、詳細な事業計画書、事業の安定性・継続性を証明する資料(取引先の契約書、資金調達計画など)が必要になる場合があります。
会社の事業の安定性や継続性を慎重に審査するため、他のカテゴリーに比べて審査期間が長くなり、ほとんどの場合在留期間は「1年」となります。
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」【出入国在留管理庁】

就労ビザの申請方法
申請フローの詳細
就労ビザの申請は、主に「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを通じて行われ、以下のステップで進行します。
1.在留資格認定証明書交付申請
日本の雇用企業が申請人(外国人)の代わりに入管に申請
2.審査・交付(1-3か月)
出入国在留管理庁による書類審査
3.証明書の海外送付
交付された証明書を申請人に郵送
4.査証申請
申請人が現地の日本領事館でビザ申請
5.来日・在留カード交付
入国後、空港または入管で在留カード受領
必要書類のリスト
全カテゴリー共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm、申請前3か月以内撮影)
- 返信用封筒(簡易書留用)
- カテゴリー証明書類
- 専門士・高度専門士証明書(該当者のみ)
カテゴリー3・4の追加書類
- 労働条件通知書(雇用契約書)
- 履歴書
- 卒業証明書または職歴証明書
- 登記事項証明書
- 会社案内書
- 決算文書の写し
- 法定調書合計表(カテゴリー3のみ)
申請時の注意点
- すべての日本発行書類は発行日から3か月以内のものを提出
- 外国語書類には日本語訳文を添付
- 原本返却希望の場合は申請時に申告が必要
- 追加書類提出を求められる場合がある
オンライン申請ステムについて
出入国在留管理庁では「在留申請オンラインシステム」を提供しており、一定の条件を満たす機関では電子申請が可能です。
24時間いつでも申請が可能、窓口への来庁不要、審査状況のオンライン確認、書類の電子提出など、メリットが多く、活用する方が増えています。
出入国在留管理庁のサイトでもオンライン手続きが便利ですと紹介されています。
就労ビザの審査と発給
就労ビザの審査期間は標準処理期間として1-3か月とされていますが、実際の期間は申請内容や審査の混雑状況により変動します。
審査では以下の点が重点的にチェックされます。
- 適合性審査:在留資格の要件との適合性
- 真実性審査:提出書類の真実性
- 相当性審査:日本の利益・安全への影響
不許可になる主な原因
1. 職務内容と学歴・職歴の不一致
最も多い不許可理由。文系大学卒業者が工場のライン作業に従事する場合など、専門性との関連性が認められないケース。
2. 提出書類の不備・不足
必要書類の漏れ、期限切れ書類の提出、記載内容の矛盾など。
3. 雇用企業の信頼性不足
経営状況の悪化、税務上の問題、過去の入管法違反歴など。
4. 報酬の不適正
同種業務の日本人より著しく低い給与設定。
5. 申請内容の虚偽
学歴詐称、職歴の偽装、偽造書類の使用など。
就労ビザの有効期間と更新方法
就労ビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「3月」の4種類があります。
初回申請では通常1年が許可され、更新により段階的に長期間の許可を得ることができます。
カテゴリー1・2はこの限りではありません。
更新申請は在留期限の3か月前から可能で、以下の書類が必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートと在留カード
- 住民票の写し
- 課税(所得)証明書
- 納税証明書
- 在職証明書

特定の職業に必要なビザ
| 職業分野 | 適用される在留資格 | 特別な要件 |
|---|---|---|
| 医療従事者 | 医療 | 日本の国家資格取得 |
| 法務・会計専門家 | 法律・会計業務 | 外国法事務弁護士等の資格 |
| 研究者 | 研究 | 研究機関との契約 |
| 語学教師 | 教育 | 教育機関での勤務 |
| 調理師 | 技能 | 10年以上の実務経験 |
アルバイト雇用の可否(資格外活動許可)
就労ビザ保持者が副業やアルバイトを行う場合は「資格外活動許可」の取得が必要です。
ただし、以下の制限があります。
- 週28時間以内の労働時間
- 風俗営業関連業務は禁止
- 本来の在留資格活動に支障がないこと
- 事前の入管への申請と許可取得
留学生の就職活動と特定活動ビザ
大学や専門学校を卒業した留学生が就職活動を継続する場合、「特定活動(就職活動)」への在留資格変更が可能です。
この在留資格は下記の要件となっています。
- 最大1年間の在留が可能(6か月+6か月更新)
- 資格外活動許可により週28時間のアルバイト可能
- 大学等の推薦状が必要
- 継続的な就職活動の実施が条件
就労ビザ取得にかかる費用
| 申請種類 | 手数料(2025年8月時点) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付 | 無料 |
| 在留資格変更許可 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 |
| 在留期間更新許可 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 |
| 査証発給(海外領事館) | 3,000円(単次) |
その他費用
- 各種証明書発行費用:数百円~数千円
- 翻訳費用:1ページ3,000円~5,000円
- 郵送費:数百円
- 交通費:入管への往復費用
2025年4月から手数料が改定されており、永住許可申請10,000円。再入国許可(1回)4,000円、再入国許可(数次)7,000円に改定されています。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
専門家に依頼時の費用相場
行政書士や弁護士に就労ビザ申請を依頼する場合、内容に異なりますが、一般的に下記が相場になります。
- 在留資格認定証明書交付申請:10万円~20万円
- 在留資格変更許可申請:8万円~15万円
- 在留期間更新許可申請:5万円~10万円
- 不許可案件の再申請:15万円~30万円
費用は事案の複雑さ、書類作成の工数、成功報酬の有無により変動するので、事前に確認するようにしましょう。

就労ビザ以外の在留資格
日本の在留資格は29種類に分類され、大きく以下のカテゴリーに分けられます。
就労制限なし(身分・地位系)
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
就労可能(活動系)
- 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
- 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療
- 研究、教育、技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
原則就労不可
- 文化活動、短期滞在、留学、研修
- 家族滞在、特定活動(一部を除く)
29種類の在留資格に関しては下記記事で詳しく解説しております。
【完全ガイド】在留資格29種類を徹底解説!取得方法や就労可否も紹介
就労ビザとの違い
| 項目 | 就労系在留資格 | 身分・地位系 |
|---|---|---|
| 活動制限 | 許可された範囲内のみ | 制限なし |
| 転職 | 入管への届出または許可必要 | 自由 |
| 永住権取得 | 10年在留必要 | 3年在留で可能 |
| 更新要件 | 活動実績が重要 | 素行・生計要件中心 |
特定技能ビザの特徴
- 対象分野:介護、建設、農業など12分野に限定
- 技能要件:技能試験合格または技能実習修了
- 日本語要件:基本的な日本語能力(N4レベル等)
- 在留期間:1号は通算5年、2号は長期在留可能
- 家族帯同:1号は不可、2号は可能
- 転職:同一分野内であれば可能
就労ビザ申請での失敗事例と対策
事例1:職務内容と学歴の不一致
失敗事例:文学部卒業の外国人がプログラマーとして申請し不許可
対策:職業訓練校での学習歴や独学での技術習得を証明する資料を追加提出
事例2:雇用企業の安定性不足
失敗事例:設立間もない小規模企業で財務状況が不安定
対策:詳細な事業計画書、資金調達計画、取引先との契約書等で事業継続性を証明
事例3:書類の不備・不足
失敗事例:卒業証明書の有効期限切れ、翻訳の漏れ
対策:提出前チェックリストの作成と第三者による書類確認
就労ビザ取得における専門家の活用
行政書士や弁護士などの専門家に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 高い許可率:専門知識による適切な申請書作成
- 時間短縮:書類作成や手続きの代行
- リスク軽減:不許可リスクの事前回避
- 継続サポート:更新手続きや変更手続きの対応
- 最新情報の提供:法改正や実務変更の情報提供

行政書士と弁護士の違い
| 項目 | 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 入管申請取次 | ○(届出済み行政書士) | ○ |
| 費用相場 | 比較的低額 | 比較的高額 |
| 裁判対応 | × | ○ |
| 専門性 | 入管業務特化が多い | 総合的法律サービス |
初回申請で要件が複雑な場合や、過去に不許可歴がある場合は専門家に依頼すると安心です。
また、申請時期が限られている、申請人の日本語能力が限定的な場合も専門家に依頼するようにしましょう。
カテゴリー1・2の大企業での単純更新や、過去の申請で問題がなかった、入管手続きの知識がある方は自分での申請を検討して良いと思われます。
まとめ
就労ビザの取得は、日本での就労を実現するための重要な第一歩です。
この記事では就労ビザの基本から申請の方法まで詳しく解説いたしました。
就労ビザの申請は複雑な手続きですが、適切な準備と正確な書類作成により、成功の可能性を大きく高めることができます。不明な点がある場合は、出入国在留管理庁への相談や専門家への依頼を積極的に検討することをお勧めします。
日本での就労を通じて、国際的なキャリアを築いていくための第一歩として、本記事の情報を活用していただければ幸いです。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 

-
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。


-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る