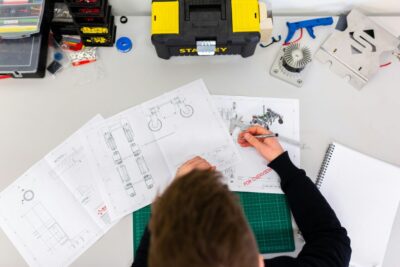特別高度人材制度(J-SKIP)とは?年収と学歴・職歴の要件を専門家が徹底解説
ビザ(在留資格)申請サポート

2023年4月から、日本の在留資格制度に新たな道が開かれました。それが「特別高度人材制度(J-SKIP)」です。この制度は、世界中から特に優れた能力を持つ人材を日本に呼び込むことを目的としており、従来の高度専門職制度よりもさらに手厚い優遇措置が設けられています。
「自分の経歴なら、もしかしたら対象になるかもしれない」「どのようなメリットがあるのだろうか」と関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし、新しい制度であるため情報が少なく、ご自身の状況に当てはめて考えるのは難しいかもしれません。
この制度は、単に新しい在留資格というだけでなく、日本の国際競争力を高めるための重要な一手であり、対象となる方にとっては、日本でのキャリアと生活の可能性を大きく広げるチャンスとなります。
こちらの記事では、特別高度人材制度(J-SKIP)の具体的な内容や要件、そしてそのメリットについて詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
特別高度人材制度(J-SKIP)とは?制度の全体像を理解する
近年、世界的な人材獲得競争が激化する中、日本が国際社会での競争力を維持・強化していくためには、特に優れた能力を持つ外国籍人材の受け入れが不可欠です。そこで、従来の「高度専門職」制度をさらに発展させる形で、2023年4月に導入されたのが「特別高度人材制度(J-SKIP)」です。
この制度は、まさに「選ばれた人材」のための特別な制度であり、学術研究や経済分野でトップレベルの実績を持つ方を対象としています。従来のポイント制とは異なり、一定の高い年収と職歴または学歴という、より明確な基準で対象者を認定するのが大きな特徴です。
この制度を利用することで、対象者はこれまでの在留資格では考えられなかったような、非常に手厚い優遇措置を受けることができます。
J-SKIPが創設された背景
J-SKIPが創設された背景には、深刻化する人材獲得競争があります。欧米諸国やアジアの主要国では、以前からトップレベルの人材を惹きつけるための優遇制度が整備されていました。
例えば、シンガポールの「ONE Pass」やイギリスの「High Potential Individual visa」などがそれに当たります。これらの国々と伍していくために、日本もより魅力的な制度を提示する必要に迫られました。
従来の高度専門職制度はポイント制であり、学歴、職歴、年収などを細かく点数化して判断していましたが、世界トップレベルの人材から見ると、手続きが煩雑で、必ずしも魅力的な制度とは言えませんでした。そこで、より分かりやすく、かつ国際的に見ても遜色のない優遇措置を与える制度としてJ-SKIPが誕生したのです。
従来の高度専門職制度との違い
J-SKIPと従来の高度専門職制度の最も大きな違いは、認定の基準です。
高度専門職制度は、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などの項目をポイントに換算し、合計70点以上で認定される「ポイント制」です。申請者は自身の経歴を証明する多くの書類を準備し、ポイント計算を行う必要がありました。
一方、J-SKIPはポイント計算が不要です。「学歴または職歴」と「年収」という2つのシンプルな基準を満たせば認定されます。これにより、申請プロセスが大幅に簡素化され、対象者にとっての分かりやすさが格段に向上しました。
また、後述する優遇措置の内容も、J-SKIPの方が従来の高度専門職よりもさらに手厚いものとなっています。特に、在留期間が無期限の「特別高度人材(J-SKIP)ビザ」が直接付与される点は、日本での長期的なキャリアと生活を考える上で非常に大きなメリットと言えるでしょう。
J-SKIPの具体的な要件は?2つのルートを徹底解説
特別高度人材(J-SKIP)として認定されるためには、どのような条件をクリアする必要があるのでしょうか。J-SKIPには、活動内容に応じて「研究者・技術者ルート」と「経営者・管理者ルート」という2つの明確な区分が設けられています。
ご自身の経歴がどちらのルートに該当するのか、そしてそれぞれのルートで定められた「学歴・職歴」と「年収」の基準を満たしているかを確認することが、申請への第一歩となります。ここでは、それぞれのルートの具体的な要件について、分かりやすく解説していきます。
ルート1:研究者・技術者(高度専門職1号イまたはロに該当する活動)
こちらのルートは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導、もしくは教育をする活動、または自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務に従事する活動を行う方が対象です。具体的には、大学教授や研究者、企業のエンジニアなどが該当します。
このルートで認定されるためには、以下のAとBの両方を満たす必要があります。
- A:修士号以上の学位を持っていること、または10年以上の実務経験があること
- B:年収が2,000万円以上であること
「実務経験」とは、従事しようとする研究、教育、または業務に関連する分野での経験を指します。例えば、ITエンジニアとして10年以上のキャリアがあり、年収が2,000万円以上であれば、大学を卒業していなくてもこのルートの対象となる可能性があります。
ルート2:経営者・管理者(高度専門職1号ハに該当する活動)
こちらのルートは、日本の公私の機関で事業の経営を行い、または管理に従事する活動を行う方が対象です。具体的には、企業の経営者や役員、部長クラス以上の管理職などが該当します。
このルートの要件は、研究者・技術者ルートよりもさらに高い水準が求められ、以下のAとBの両方を満たす必要があります。
- A:事業の経営または管理について5年以上の実務経験があること
- B:年収が4,000万円以上であること
ここでの「年収」とは、役員報酬や給与の総額を指します。例えば、外資系企業の日本法人の代表として赴任し、5年以上の経営経験があり、年収が4,000万円以上の場合、このルートでの申請が考えられます。
このように、J-SKIPの要件は非常に明確です。ご自身の経歴と収入がこれらの基準を満たしているか、まずは確認してみてください。
J-SKIPで得られる7つの優遇措置とは?
厳しい要件をクリアして特別高度人材(J-SKIP)として認定されると、どのようなメリットがあるのでしょうか。J-SKIPでは、日本での活動や生活を強力にサポートするため、従来の在留資格にはない、非常に手厚い7つの優遇措置が用意されています。
これらの優遇措置は、ご自身のキャリアの可能性を広げるだけでなく、ご家族の生活にも大きな安心をもたらします。ここでは、J-SKIPで得られる具体的なメリットを一つひとつ詳しく見ていきましょう。
1. 在留期間「5年」の付与と無期限の在留資格「特別高度人材」
J-SKIPの最大のメリットは、在留資格の安定性です。まず、J-SKIPの対象者には、在留資格「特定活動」が付与され、在留期間として一律で最長の「5年」が与えられます。
さらに、この「特定活動」の在留資格で1年間活動を行うと、在留期間が無期限の在留資格「特別高度人材」への変更が可能になります。これは、実質的に永住権と同様の安定した地位を、わずか1年で得られることを意味し、将来設計を立てる上で非常に大きなアドバンテージとなります。
2. 複合的な在留活動の許容
通常の就労ビザでは、許可された範囲の活動しか行うことができません。例えば、大学で研究活動を行う「教授」ビザを持つ人が、知識を活かしてベンチャー企業を経営することは原則として認められません。
しかし、J-SKIPでは、複数の在留資格にまたがるような複合的な活動が許容されます。これにより、研究者が自らの研究成果を基に会社を設立したり、経営者が大学で教鞭をとったりと、自身の能力を最大限に活かした多角的なキャリア展開が可能になります。
3. 配偶者の就労要件の大幅な緩和
外国人材が日本で活躍するためには、家族のサポートが不可欠です。J-SKIPでは、配偶者の就労に関しても大幅な緩和措置が取られています。
通常、配偶者が「家族滞在」ビザで就労する場合、週28時間以内の資格外活動許可の範囲に限られます。しかし、J-SKIP対象者の配偶者は、学歴や職歴の要件を満たすことなく、また就労時間の制限もなく、研究、語学教育、エンジニア、国際業務といった幅広い職種でフルタイムの就労が可能です。これにより、配偶者も自身のキャリアを諦めることなく、日本で活躍することができます。
4. 一定条件下での親の帯同
幼い子供を育てる世帯にとって、親のサポートは非常に心強いものです。J-SKIPでは、一定の条件下で本人または配偶者の親(70歳未満でも可)の帯同が認められます。
主な条件は、世帯年収が800万円以上であること、そしてJ-SKIP対象者の7歳未満の子供の養育、または妊娠中の本人や配偶者の介助を行うことです。これにより、安心して子育てができる環境が整います。
5. 一定条件下での家事使用人の帯同
多忙な日々を送る高度人材にとって、家事の負担は大きな課題です。J-SKIPでは、一定の条件下で外国人の家事使用人を帯同することが認められています。
主な条件として、世帯年収が1,000万円以上であること、帯同できる家事使用人は1名まで、そして月額20万円以上の報酬を支払うことなどが定められています。これにより、仕事に集中できる環境を確保することができます。
6. 入国・在留手続の優先処理
出入国在留管理庁での手続きは、時に長い時間を要することがあります。しかし、J-SKIPに関連する申請は、他の申請に優先して早期に処理されます。
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)であれば約10営業日、在留資格変更許可申請(国内での切り替え)であれば約5営業日という、迅速な審査が期待できます。
7. 主要な空港での優先レーンの利用
出張や一時帰国で空港を利用する機会も多いでしょう。J-SKIP対象者は、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港などの主要な空港で優先レーンを利用でき、スムーズに出入国審査を通過することができます。
J-SKIP申請の注意点と必要書類
特別高度人材(J-SKIP)の申請は、要件が明確である一方、その証明は慎重に行う必要があります。特に「年収」や「実務経験」の立証は、審査の根幹をなす重要なポイントです。
例えば、年収の証明では、単に契約書上の金額だけでなく、賞与やインセンティブの取り扱いをどう説明するかが問われます。また、実務経験の証明では、過去の在籍証明書や職務内容を詳細に記した書類が必要となり、準備に手間がかかることも少なくありません。ここでは、申請にあたっての注意点と、一般的に必要となる書類について解説します。
申請における注意点
J-SKIPの申請で最も重要なのは、要件を満たしていることを客観的な資料で立証することです。
- 年収の証明: これから日本で活動する場合、雇用契約書や役員報酬の決定書などで「見込み年収」を証明します。この際、基本給と賞与が明確に区別されているか、変動報酬が含まれる場合はその計算根拠を合理的に説明できるかが重要です。すでに日本で活動している場合は、住民税の課税証明書や納税証明書が公的な証明となります。
- 学歴・職歴の証明: 修士号以上の学位は、大学が発行した卒業証明書や学位記の写しで証明します。実務経験は、過去に在籍した企業からの在籍証明書や退職証明書に加え、具体的な職務内容、役職、在籍期間が明記された書類(職務経歴書や推薦状など)を準備する必要があります。特に、職務内容が申請する活動内容と関連していることを明確に示すことが求められます。
- 申請のタイミング: J-SKIPは、海外から日本に来る際の「在留資格認定証明書交付申請」と、すでに他の在留資格で日本にいる場合の「在留資格変更許可申請」のどちらでも申請が可能です。ご自身の状況に合わせて適切な手続きを選択する必要があります。
必要書類
申請に必要な書類は、個々の状況や活動内容によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要となります。
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 学歴又は職歴を証明する資料(卒業証明書、在籍証明書など)
- 年収を証明する資料(雇用契約書の写し、住民税の課税・納税証明書など)
- 活動内容を明らかにする資料(所属機関の概要が分かる資料など)
- (該当する場合)親や家事使用人の帯同に関する資料
これらの書類はあくまで一例です。実際の申請では、出入国在留管理庁の担当官から追加の資料提出を求められることもあります。スムーズな手続きのためには、専門家である行政書士に相談し、ご自身の状況に合わせた万全の準備をすることが賢明です。
まとめ
この記事では、2023年4月から始まった新しい在留資格制度「特別高度人材制度(J-SKIP)」について、その創設の背景から具体的な要件、そして魅力的な優遇措置までを詳しく解説しました。
J-SKIPは、従来のポイント制とは異なり、「年収」と「学歴・職歴」という明確な基準で世界トップレベルの人材を認定する制度です。
対象となる方には、無期限の在留資格への道がわずか1年で開かれるほか、複合的な活動の許容、配偶者のフルタイム就労、親や家事使用人の帯同など、これまでの在留資格の常識を覆すような手厚い優遇措置が与えられます。
ご自身の経歴がJ-SKIPの要件に該当する可能性があると感じた方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。申請には、年収や職歴を客観的に証明するための入念な書類準備が不可欠です。私たち行政書士は、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な形で申請をサポートいたします。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 

-
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。


-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る