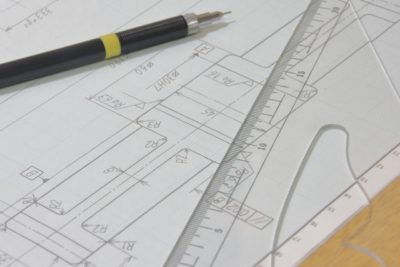【徹底解説】「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の全知識
ビザ(在留資格)申請サポート

日本で働くことを希望する外国人の方々にとって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は非常に重要なものです。この在留資格は、専門的な知識や技術、あるいは国際的な感性を活かした業務に従事するために必要とされます。しかし、その取得には複雑な要件や多くの書類準備が伴い、初めて申請する方にとっては戸惑うことも少なくありません。
例えば、大学で専門分野を学んだ方がその知識を活かして日本企業で働く場合や、語学力を活かして翻訳・通訳の仕事に就く場合など、多岐にわたる職種がこの在留資格の対象となります。しかし、単に学歴や職務経験があるだけでは許可されず、実務経験の年数や報酬額、さらには企業側の状況など、様々な要素が総合的に審査されます。
特に、近年は入管法の改正や審査基準の厳格化が進んでおり、以前にも増して慎重な準備が求められています。不許可となってしまうと、再申請には時間も労力もかかり、日本でのキャリアプランに大きな影響を及ぼす可能性もあります。そのため、申請前には十分な情報収集と適切な準備が不可欠です。
こちらの記事では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、その取得要件から申請手続き、注意点までを詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で働く外国人が取得する就労ビザの一つであり、その名の通り、専門的な「技術」、人文科学分野の「知識」、または国際的な「業務」に従事する外国人を対象としています。このビザは、単なる肉体労働ではなく、専門性や知見を活かした業務を行う外国人に与えられるもので、日本の産業や文化の発展に貢献することを目的としています。
具体的には、ITエンジニア、デザイナー、通訳、翻訳家、語学教師、企業の海外事業担当者など、多岐にわたる職種がこの在留資格の対象となります。これらの職種は、それぞれ異なる専門性やスキルが求められるため、申請時には個々の業務内容に応じた詳細な説明と、それを裏付ける学歴や職務経歴の証明が不可欠となります。
この在留資格は、日本企業がグローバル化を進める上で、海外の優秀な人材を確保するために重要な役割を果たしています。例えば、日本の製造業が海外市場に進出する際に、現地の文化や商習慣に精通した人材が必要となる場合や、IT企業が最新の技術を取り入れるために、海外の高度な技術を持つエンジニアを招へいするケースなどが挙げられます。このように、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本経済の活性化にも寄与していると言えるでしょう。
専門的技術・知識を要する業務とは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となる業務の一つに、専門的な技術や知識を必要とする業務があります。これは、大学や専門学校で習得した専門知識や、長年の実務経験を通じて培われた技術を活かして行う業務を指します。例えば、システムエンジニア、建築士、機械設計者、商品開発者などがこれに該当します。
この要件を満たすためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 大学を卒業していること。(従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していること。)
- 日本の専修学校を卒業していること。(従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していること。)
- 従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること。(大学等で従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していた期間を含む。)
ここで重要なのは、単に学歴があるだけでなく、その学歴が従事する業務と関連していることです。例えば、経済学を専攻した方がITエンジニアとして働く場合、その関連性を明確に説明する必要があります。また、実務経験で申請する場合、10年以上の経験が必要とされ、その経験が申請する業務内容と密接に関連していることが求められます。実務経験には、大学などで関連科目を専攻していた期間も含まれるため、学歴と実務経験を組み合わせて要件を満たすことも可能です。
国際的な感性を要する業務とは?
もう一つの対象業務は、外国人特有の感性や文化的な背景を必要とする業務です。これは、国際的なビジネスや文化交流において、外国人の視点や言語能力が不可欠な業務を指します。具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や内装装飾に係るデザイン、商品開発などが挙げられます。
この要件を満たすためには、以下のいずれにも該当する必要があります。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは内装装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。
ただし、大学を卒業した方が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要とされています。これは、これらの業務が高度な語学力や専門知識を必要とし、大学での教育がその基礎を十分に提供すると考えられているためです。例えば、日本語と英語のバイリンガルで、日本の大学で文学を専攻した方が、日本の出版社で海外文学の翻訳を担当するようなケースがこれに該当します。
このタイプの業務では、単に言語ができるだけでなく、異文化理解や国際的なコミュニケーション能力が重視されます。そのため、申請時には、これまでの職務経験や学歴が、どのように国際的な感性を必要とする業務に活かされるのかを具体的に説明することが求められます。
専攻と業務の具体的な例
以下は、国が示している専攻と業務内容の具体的な例です。
| 専攻 | 業務内容 |
| 工学 | オンラインゲームのシステム設計、総合試験、検査 |
| 電気通信工学 | コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務 |
| 機械工学 | 自動車メーカーで技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務 |
| 工学,情報処理等 | 証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発、また取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務 |
| 建築工学 | 建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務 |
| 社会基盤工学 | 土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務 |
| 電気力学,工学等 | CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務 |
| 電子情報学 | 情報セキュリティプロジェクトに関する業務 |
| ― | 語学教師としての業務 |
| 経営学 | 外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務 |
| 会計学 | 本国の会社との貿易等に係る会計業務 |
| 国際関係学 | 語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務 |
| 経営学 | 本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務 |
| 経営学 | 本国との取引業務における通訳・翻訳業務 |
| 経済学,国際関係学 | 国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務 |
| 経営学 | 国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務 |
(出典:法務省 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)
在留資格取得のための必須要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、前述の専門性や国際的な感性に関する要件だけでなく、いくつかの必須要件を満たす必要があります。これらの要件は、申請者の日本での安定した生活と、日本社会への貢献を担保するために設けられています。特に重要なのが、報酬に関する要件と、雇用する企業側の状況です。
報酬に関する要件は、申請者が日本で安定した生活を送るための経済的基盤があるか、そして外国人であることを理由に不当に低い賃金で雇用されていないかを判断するために設けられています。これは、外国人労働者の保護と、日本国内の労働市場の適正な維持を目的としています。
例えば、あるIT企業が海外から優秀なエンジニアを招へいする場合、そのエンジニアに支払われる報酬が、同じ企業で同等の業務に従事する日本人従業員と比較して適正であるかどうかが厳しく審査されます。もし、外国人エンジニアの報酬が日本人従業員よりも著しく低い場合、それは不当な労働条件とみなされ、ビザの許可が下りない可能性があります。
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する上で、最も重要な経済的要件の一つが、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」です。これは、外国人であることを理由に不当に低い賃金で雇用されることを防ぎ、日本人労働者との賃金格差をなくすことを目的としています。
具体的には、申請者が従事しようとする業務内容や役職、経験、能力などを考慮し、同じような条件で働く日本人従業員が受け取るであろう給与水準と同等か、それ以上の報酬が支払われる必要があります。この「報酬」には、基本給だけでなく、各種手当(通勤手当、扶養手当、住宅手当など)が含まれる場合と含まれない場合がありますので注意が必要です。
入管法における「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」を指します。この定義に基づくと、通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は、原則として報酬には含まれません。つまり、これらの手当を除いた基本給や職務手当などが、日本人と同等以上であるかどうかが審査の対象となります。
例えば、月給30万円の日本人社員がいる会社で、同じ業務内容の外国人を月給25万円で雇用しようとした場合、この要件を満たさない可能性があります。企業は、外国人従業員を雇用する際に、その業務内容や責任に見合った適正な報酬を支払う義務があるのです。これは、外国人労働者の権利保護だけでなく、日本国内の労働市場の健全性を保つ上でも非常に重要な原則となります。
申請手続きの流れと必要書類
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際には、適切な手続きを踏み、必要な書類を漏れなく提出することが不可欠です。手続きの流れを正確に理解し、事前にしっかりと準備を行うことで、スムーズな審査と許可への道が開かれます。ここでは、一般的な申請の流れと、その際に必要となる主要な書類について詳しく解説します。
申請手続きは、大きく分けて「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2種類があります。海外から日本に初めて入国して就労する場合、まずは「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認定証明書が交付された後に、本国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受け、日本に入国します。一方、すでに日本に滞在しており、別の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
どちらの申請においても、提出書類は多岐にわたり、申請人の状況や雇用する企業の種類によっても異なります。例えば、企業が上場企業であるか、中小企業であるかによって、提出を求められる書類の範囲が変わることもあります。また、申請人の学歴や職務経歴、日本での活動内容を具体的に示す資料も重要です。これらの書類が不十分であったり、内容に矛盾があったりすると、審査が長期化したり、最悪の場合、不許可となる可能性もあります。
申請手続きの一般的な流れ
在留資格の申請は、以下のステップで進められます。
- 必要書類の収集と作成:申請に必要な書類をリストアップし、収集・作成します。企業側が準備する書類と、申請人自身が準備する書類があります。
- 申請書の作成:入国管理局のウェブサイトからダウンロードできる申請書に、正確かつ詳細な情報を記入します。
- 入国管理局への申請:準備が整った書類一式を、管轄の地方出入国在留管理局に提出します。郵送または窓口での申請が可能です。
- 審査:入国管理局による審査が行われます。追加資料の提出を求められることもあります。
- 結果通知:審査が完了すると、結果が通知されます。許可の場合、在留カードの交付や、在留資格認定証明書の交付が行われます。
主要な必要書類リスト
以下に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請において一般的に必要となる書類の例を挙げます。個別の状況により、これ以外の書類が必要となる場合もありますので、詳細は専門家にご相談いただくか、入国管理局のウェブサイトをご確認ください。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(日本に滞在中の場合)
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
- 職務経歴書(職務経験を証明する場合)
- 雇用契約書の写し
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算報告書(直近1年分)
- 会社案内、事業内容を説明する資料
- 源泉徴収票(日本に滞在中の場合)
- 住民税の課税証明書および納税証明書(日本に滞在中の場合)
不許可事例から学ぶ注意点と対策
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請は、要件が多岐にわたり、提出書類も複雑であるため、残念ながら不許可となってしまうケースも少なくありません。不許可の理由は様々ですが、多くの場合、申請内容の不備や、入国管理局が求める要件を十分に満たしていないことが原因です。ここでは、よくある不許可事例とその対策について解説します。
不許可の通知を受け取ると、多くの方が落胆し、今後のキャリアプランに不安を感じるかもしれません。しかし、不許可は必ずしも最終的な判断ではありません。不許可の理由を正確に把握し、適切な対策を講じることで、再申請での許可を目指すことが可能です。重要なのは、なぜ不許可になったのかを冷静に分析し、その原因を解消することです。
例えば、ある外国人の方が日本のIT企業で働くために「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請したとします。しかし、大学での専攻がITとは直接関係のない分野であったため、入国管理局から「専門性との関連性が不明確」として不許可の通知を受けました。この場合、単に学歴だけを提示するのではなく、これまでの職務経験や自己学習を通じてどのようにITスキルを習得し、それが今回の業務にどのように活かされるのかを具体的に説明する追加資料を提出することで、再申請での許可を得られる可能性があります。
よくある不許可事例とその対策
不許可となる主な原因は以下の通りです。
- 学歴・職務経歴と業務内容の不一致:申請者の学歴や職務経歴が、従事しようとする業務内容と関連性が低いと判断されるケースです。
対策:業務内容と学歴・職務経歴の関連性を具体的に説明する理由書や、関連する実務経験を証明する書類を詳細に提出することが重要です。必要であれば、業務内容をより専門的に説明する資料も添付します。
- 報酬額の不適正:日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が支払われないと判断されるケースです。
対策:雇用契約書の内容を見直し、日本人従業員との報酬比較表などを提出して、報酬の適正性を明確に示します。手当の内訳なども詳細に記載することが求められます。
- 会社の安定性・継続性の問題:雇用する企業が、外国人を受け入れるだけの経営基盤や事業の安定性・継続性がないと判断されるケースです。
対策:会社の決算状況、事業計画、従業員数などを詳細に説明する資料を提出し、企業の健全性をアピールします。特に、設立間もない企業の場合は、事業の具体性や将来性をより丁寧に説明する必要があります。
- 提出書類の不備・不足:必要書類が揃っていない、または記載内容に誤りや矛盾があるケースです。
対策:申請前に全ての書類を再度確認し、漏れや誤りがないかを徹底的にチェックします。不明な点があれば、入国管理局や専門家に相談し、正確な情報を記載することが重要です。
これらの不許可事例は、いずれも事前の準備と正確な情報提供によって回避できる可能性が高いものです。もし不許可となってしまった場合でも、諦めずに専門家のアドバイスを求め、再申請に向けて準備を進めることが大切です。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で専門的な知識や技術、国際的な感性を活かして働きたい外国人にとって、非常に重要な就労ビザです。この在留資格を取得するためには、学歴や職務経歴、業務内容、報酬など、多岐にわたる要件をクリアし、適切な書類を準備して申請を行う必要があります。
特に、学歴と業務内容の関連性、日本人と同等以上の報酬、そして雇用する企業の安定性・継続性は、審査において厳しくチェックされるポイントです。これらの要件を十分に満たしていない場合や、提出書類に不備がある場合には、不許可となるリスクが高まります。しかし、不許可となった場合でも、その理由を正確に分析し、適切な対策を講じることで、再申請での許可を目指すことは十分に可能です。
複雑な申請手続きや、多岐にわたる必要書類の準備は、専門知識がないと非常に困難に感じられるかもしれません。また、入管法の改正や審査基準の変更など、常に最新の情報を把握しておくことも重要です。そのため、ご自身での申請に不安を感じる場合や、より確実に許可を得たいと考える場合には、入管業務を専門とする行政書士などの専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
専門家は、個々の状況に応じた的確なアドバイスを提供し、必要書類の収集から申請書の作成、入国管理局とのやり取りまで、一貫してサポートしてくれます。これにより、申請の負担を軽減し、許可の可能性を高めることができるでしょう。日本でのキャリアを成功させるためにも、この「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は、計画的かつ慎重に進めることが何よりも大切です。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 

-
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。


-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る