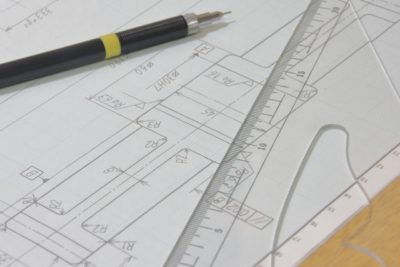技術・人文知識・国際業務ビザに必要な学歴とは?専門家が徹底解説
ビザ(在留資格)申請サポート

外国人が日本でホワイトカラー職に就くために利用される代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。しかしこのビザには、「学歴要件」と呼ばれる一定の学歴基準をクリアする必要があるため、申請前にしっかりとした確認が欠かせません。
「大学を卒業していれば問題ないの?」
「専門学校は対象になる?」
そんな疑問を持つ方も多いはずです。
こちらの記事では、「技術・人文知識・国際業務ビザ」における学歴要件について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
技術・人文知識・国際業務ビザとは
この在留資格は、いわゆる「ホワイトカラー」の仕事に従事する外国人のためのビザで、文系・理系問わず活用されています。就職先の業種や職務内容によって必要な条件が異なりますが、申請者本人の学歴が大きな判断材料になります。
対象となる主な職種
- 通訳・翻訳、語学講師
- 営業・企画・マーケティング
- システムエンジニア・プログラマー
- 設計・製図・開発職
ビザ審査における「学歴」の重み
ビザ審査では、職務内容が「学歴に見合った内容かどうか」が非常に重視されます。
たとえば、文学部を卒業した方がIT企業でエンジニアとして働く場合、職務内容と学歴との関連性が問われる可能性があります。
「専門性」と「職務内容」の一致がカギ
学歴が審査対象になる最大の理由は、「専門性のある知識を活かして働く職種」であることが前提となっているからです。
学歴要件の基本的な考え方
「学歴」と一口にいっても、日本での基準に照らしてどう評価されるかが問題となります。入管法上での扱いを明確に理解しておくことが重要です。
大学卒業(学士、修士、博士)
最もスタンダードな要件です。出身国で「大学」に該当する機関を卒業していることが条件です。文系・理系は問われませんが、「職務との関連性」は求められます。
短期大学・高等専門学校卒業
一部のケースで認められるものの、大学卒に比べると審査はやや厳しくなる傾向にあります。
専門学校(日本)を卒業した場合(専門士、高度専門士)
専門士の称号を得ていれば学歴要件を満たすと見なされる場合があります。ただし、学校が認可された教育機関であり、修業年限も基準を満たしている必要があります。
尚、海外の専門学校卒業の場合は学歴要件としては認められていないため、後述の実務経験による申請を目指すこととなります。
「学士」「修士」「博士」「専門士」「高度専門士」の違いとは?
一般的には、大学を卒業した人を大卒者などと呼ぶことが多いですが、大学と大学院では与えられる学位は異なるものになります。
この学位についてもう少し詳細に見ていきたいと思います。
学士(Bachelor)
大学を修了した際に与えられる基本的な学位が「学士号」です。英語では “Bachelor’s Degree” と表記され、多くの人が「大卒」と認識している資格は、この学士号に該当します。
特別な資格のように思われがちですが、大学で所定の授業を受け、必要な単位を修得し、卒業論文などを提出して課程を終えた人には、卒業と同時に学士の学位が自動的に授与されます。つまり、一般的な4年制大学を問題なく卒業すれば、学士号は自然に取得できるものです。
また、2年制の短期大学を修了した場合には、「短期大学士」という別の学位が付与されます。これは学士号とは異なる名称の学位で、短大独自の教育課程を修了した証明となります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、この学士の称号を有することが最も基本的な要件の一つです。職務内容と学位の関連性があれば、審査も比較的スムーズに進みます。
修士(Master)
修士号とは、大学院を修了した際に授与される学位で、英語では「Master’s Degree」と呼ばれます。日本では「マスター」という呼び方も一般的です。通常、2年間の大学院教育を修了し、一定の研究成果を挙げた学生に対して授与されます。
修士号を取得するには、「修士課程」または「博士前期課程」といった課程に進学し、専門性の高い研究や成果の提出が求められます。また、教職大学院などの専門職大学院を修了した場合にも、修士号が与えられます。
大学院への進学には、学士課程での学業成績や研究姿勢が重視され、指導教員からの推薦が必要となるケースも少なくありません。そのため、自身の専門分野を明確に定めたうえで進学を検討することが重要です。
なお、医学部、獣医学部、薬学部、歯学部などの6年制学部については、卒業時点で「修士号に相当する学修歴」と見なされることが一般的であり、そのまま博士課程へ進学することもあります。
実務上、修士号を持っていれば、職務との関連性が高く評価されやすく、ビザ取得において加点要素となるケースが多く見られます。
博士(Doctor)
博士号とは、大学院における最終段階の学位であり、専門分野における高度な研究成果が認められた人に与えられます。英語では「Ph.D.」あるいは「Doctor’s Degree」と表され、日本国内では「ドクター」と呼ばれることもあります。
この学位は主に2つの方法で授与されます。ひとつは、博士後期課程(または博士課程)に3年以上在籍し、指導を受けながら論文をまとめ、審査を経て合格することで得られる「課程博士」。もうひとつは、大学院に所属せずとも一定の研究実績をもとに論文を提出し、審査に合格した場合に認定される「論文博士」です。
博士課程に進むには通常、修士課程(あるいは博士前期課程)を修了してから進学するルートが一般的ですが、医学・歯学・獣医学・薬学といった6年制の専門学部を卒業した場合には、修士課程を経ずに直接博士課程へ進むことも可能です。
博士課程は、修士段階と合わせて標準で5年間とされますが、論文執筆や研究の長期化により、博士号を取得する時点で30代になっているケースも多く見られます。
また、博士号取得後は「ポストドクター(ポスドク)」として、大学や研究機関などで期間契約の研究職に就く道があります。将来的に大学教員を目指す人が多いものの、最近では一般企業へ就職し、研究開発職などで活躍する人も増加傾向にあります。
高度専門職ビザや研究者ビザなど、より高度な分野での活動を希望する場合には大きな強みとなり、在留資格の審査でも優遇される場合があります。
専門士(専門学校卒業者)
「専門士」は、日本の専修学校(専門課程)を2年以上修了し、総授業時間数1,700時間以上、試験などによる成績評価を行い、その評価に基づいて専門課程を修了した者に与えられる称号です。学校教育法に基づく正式な学位ではありませんが、法務省はこれを学歴として評価することがあります。
ただし、
- 学校が文部科学大臣または都道府県知事の認可を受けていること
- 修了後に「専門士」の称号が授与されていること
- 職務との関連性が明確であること
が必要条件です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、専門士の称号があっても、就労予定職種との整合性が強く求められます。
高度専門士
「高度専門士」は、専修学校の4年制課程を修了し、総授業時間数3,400時間以上、試験などによる成績評価を行い、その評価に基づいて専門課程を修了した者に与えられる称号です。大学卒業と同等以上とみなされることが多く、進学やビザ申請において有利に扱われる傾向があります。
特にIT、福祉、国際コミュニケーションなどの分野では、大学卒業とほぼ同等の評価がされることもあり、学士がない場合でも申請が通る可能性はあります。
よくある学歴別の可否判断
実務上、相談が多いのがこの項目です。以下に、典型的なケース別に可否の目安を紹介します。
中国の大専卒業
通常は「短大卒」と同等とされることが多く、職務との関連性や業務内容をより具体的に証明する必要があります。
通信制大学・夜間大学卒業
原則として通常の大学卒業と同様に扱われます。ただし、卒業証明書や単位取得状況の説明が求められることがあります。
高卒・職歴あり
基本的に学歴要件を満たさないとされますが、後述する「実務経験要件」での申請を検討することが可能です。
学歴以外でビザ取得は可能か?
必ずしも「大学卒」でなければならないというわけではなく、一定の条件を満たすことで学歴以外のルートからの申請も可能です。
実務経験による申請
技術・人文知識のカテゴリーであれば実務経験10年以上あれば、学歴がなくても審査対象となります。たとえばIT技術者が現場で10年以上の経験を積んでいる場合、その証明をもって申請可能です。
また、国際業務のカテゴリーであれば実務経験3年以上の実務経験があれば申請可能となります。
推薦書・職務内容証明書の提出
実務経験を証明するためには、過去の雇用先からの証明書や、業務実績をまとめた推薦書が必要です。信頼性ある資料であることが求められます。
注意点と実際の審査傾向
実務経験ルートは、審査官の裁量が大きく左右するため、十分な準備と専門家の関与が不可欠です。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの学歴要件は、形式的な学歴だけでなく、「その学歴が実際の職務にどう関連しているか」が問われるものです。大学卒業が基本要件とされていますが、日本の専門学校や外国の短大・職業訓練校でも、要件を満たせる可能性はあります。
また、学歴に不安がある場合でも、10年以上の実務経験があれば申請が可能となるケースも存在します。自身の状況を正確に把握し、適切なルートでの申請を目指すことが大切です。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 

-
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。


-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る