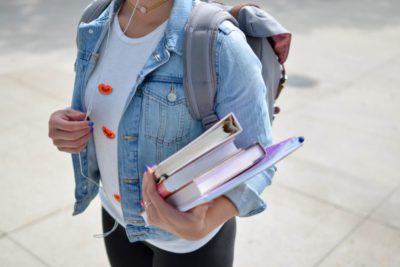家族滞在ビザの取得ガイド|要件から必要書類まで徹底解説
ビザ(在留資格)申請サポート

日本で就労ビザや留学ビザをもって活動する外国人の方が、母国にいる配偶者や子どもを呼び寄せ、共に生活したいと願うのは自然なことです。その大切な願いを叶えるための在留資格が「家族滞在」ビザです。
しかし、申請手続きは複雑で、「誰を呼べるの?」「収入はいくら必要?」「どんな書類を準備すればいいの?」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。
不備があれば、もちろん許可は下りず、家族と離れて暮らす期間が延びてしまう可能性もあります。そうした事態を避けるためには、制度を正しく理解し、慎重に準備を進めることが不可欠です。
こちらの記事では、家族滞在ビザの基本的な要件から、申請の流れ、必要書類、そして許可を得るための重要なポイントまで、専門家の視点から詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
家族滞在ビザとは?基本の「キ」を理解する
海外で暮らす家族を日本に呼び寄せたいと考えたとき、まず理解すべきなのが「家族滞在ビザ」の基本的な仕組みです。このビザは、特定の在留資格をもって日本に滞在する外国人の「扶養を受ける家族」のために設けられた制度です。ここでは、誰が対象となり、どのような活動が認められるのか、基本的な知識を分かりやすく解説します。
家族滞在ビザの対象となる「家族」の範囲
家族滞在ビザで呼ぶことができる「家族」は、扶養者の「配偶者」と「子」に限定されています。 とても重要なポイントですが、ご自身の親や兄弟姉妹を呼び寄せることは、このビザではできません。 高齢の親の面倒を見たい、といったご相談は非常に多いのですが、その場合は「特定活動」など別の在留資格を検討する必要があります。
「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある者を指します。事実婚や内縁関係のパートナーは対象外となるため注意が必要です。 また、「子」には、実子のほか、養子や認知された非嫡出子も含まれます。 年齢に明確な上限はありませんが、成年に達した子どもの場合、なぜ親の扶養が必要なのかを合理的に説明する必要があります。
扶養者が持っているべき在留資格
家族を呼び寄せる側(扶養者)が持っている在留資格も限定されています。全てのビザで家族を呼べるわけではありません。主に、日本で安定的・継続的に活動することが認められている就労ビザや留学ビザなどが対象となります。
具体的には、以下の在留資格が該当します。
- 教授、芸術、宗教、報道
- 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育
- 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能
- 文化活動、留学
一方で、「技能実習」や「特定技能1号」、「研修」、「短期滞在」などの在留資格では、原則として家族滞在ビザで家族を呼び寄せることはできません。
日本で認められる活動内容
家族滞在ビザで認められている活動は、扶養者の下で行う「日常的な活動」に限られます。 具体的には、家事、育児、学校への通学などがこれにあたります。重要なのは、このビザ単体では収入を得るための就労活動は認められていないという点です。
もし、パートやアルバイトをしたい場合は、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可を得ることで、週28時間以内の就労が可能になります。 この点については、後の章で詳しく解説します。
許可を得るための3つの重要要件
家族滞在ビザの申請が許可されるためには、いくつかの重要な要件をクリアしなければなりません。出入国在留管理庁(入管)は、申請書類を通してこれらの要件を満たしているかを厳しく審査します。ここでは、特に重要となる「家族関係の証明」「扶養能力」「扶養の必要性」という3つのポイントについて、具体的なエピソードも交えながら詳しく解説します。
【要件1】法律上の家族関係を証明できること
まず大前提として、呼び寄せる家族との関係が法律的に有効であることを公的な書類で証明する必要があります。
配偶者の場合は「結婚証明書」や「婚姻届受理証明書」、子の場合は「出生証明書」などがこれに該当します。 これらの書類は、本国で発行された原本とその日本語訳を提出するのが一般的です。
例えば、ベトナム出身のエンジニア、Aさんが母国の妻を呼び寄せようとしたケース。Aさんはベトナムの伝統的な儀式に則って結婚しましたが、役所への婚姻届の提出が遅れていました。ビザ申請の準備段階でこの事実に気づき、急いで本国の家族に連絡を取り、正式な婚姻証明書を取得してもらいました。もし気づかずに申請していたら、「法律上の婚姻関係が確認できない」として不許可になっていたでしょう。このように、公的な証明書の有無は審査の根幹をなす重要な要素です。
【要件2】家族を養う十分な経済力(扶養能力)があること
次に問われるのが、扶養者の経済力です。日本で家族と共に安定した生活を送れるだけの十分な収入や資産があることを証明しなければなりません。
明確な年収基準が公表されているわけではありませんが、一般的には、課税証明書や納税証明書に記載された年収や納税状況が審査の対象となります。 目安として、扶養者1名あたり年間70〜80万円程度の追加収入が必要とされ、夫婦2人であれば年収250万円程度が一つのラインと言われています。 もちろん、これは住んでいる地域の家賃相場や物価によっても変動します。
留学生の場合、アルバイト収入だけでは扶養能力を証明するのが難しいケースが多く、本国からの送金証明や預金残高証明書などで補う必要があります。 扶養能力の証明は、申請が不許可になる最も多い理由の一つであり、慎重な準備が求められます。
【要件3】扶養を受ける必要性を合理的に説明できること(特に子が成年に近い場合)
子が幼少期であれば、親の監護・養育が必要なのは明らかです。しかし、子どもが高校生や大学生など、成年に近い年齢の場合、「なぜ日本で親の扶養を受けて生活する必要があるのか?」という点を審査官に納得させなければなりません。
「本国で自立して生活できる年齢なのに、日本に来るのは就労が目的ではないか?」という疑念を持たれやすくなるためです。
例えば、中国出身で日本の大学院に留学しているBさんが、本国で高校を卒業したばかりの18歳の息子さんを呼び寄せようとしたケース。Bさんは申請にあたり、「息子は日本の大学への進学を強く希望しており、その準備のために親元で生活し、日本語教育を受ける必要がある」という内容の理由書を作成しました。さらに、日本の大学の資料を取り寄せ、息子さんの学習意欲を具体的に示すことで、来日の目的が就労ではなく、あくまで教育を受けるためであることを説得力をもって説明し、無事に許可を得ることができました。このように、特に子が成年に近い場合は、扶養の必要性を具体的に記述した理由書が極めて重要になります。
【ケース別】家族滞在ビザの申請手続きと必要書類
家族滞在ビザの申請は、家族が現在どこにいるかによって手続きが異なります。海外から新たに呼び寄せる場合と、すでに別のビザで日本に滞在している家族のビザを切り替える場合です。それぞれ申請の種類と必要書類が異なるため、ご自身の状況に合わせて正しく準備を進めることが重要です。ここでは、それぞれのケースにおける申請の流れと、具体的な必要書類を詳しく見ていきましょう。
海外にいる家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
家族が海外に住んでいる場合は、まず日本の出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。 この証明書は、「この外国人は日本の在留資格の条件に適合しています」ということを法務大臣が事前に証明するものです。
【申請の流れ】
- 扶養者(日本在住)が、必要書類を揃えて管轄の出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
- 審査(通常1~3ヶ月)を経て、認定証明書が交付される。
- 扶養者は、交付された認定証明書を海外の家族へ郵送する。
- 家族は、その認定証明書とパスポートなどを持って、自国の日本大使館や領事館でビザ(査証)の発給申請を行う。
- ビザが発給されたら来日。空港での上陸審査を経て、在留カードが交付され、日本での生活がスタートします。
この方法のメリットは、海外の日本大使館でのビザ発給がスムーズに進む点です。
日本にいる家族のビザを変更する場合(在留資格変更許可申請)
例えば、留学生として日本に滞在していた方が、就労ビザを持つ方と結婚した場合など、すでに別の在留資格で日本にいる家族を扶養する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【申請の流れ】
- 扶養者と申請人(家族)が、必要書類を揃えて管轄の出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を行う。
- 審査(通常2週間~1ヶ月)を経て、許可されると新しい在留カードが交付される。
この手続きは、日本国内で完結するため、一度も出国することなく在留資格を「家族滞在」に切り替えることができます。
具体的な必要書類リスト
必要書類は、扶養者の職業(会社員か経営者か)や申請人の状況によって異なりますが、ここでは一般的な「在留資格認定証明書交付申請」のケースで、会社員の方の扶養に入る場合を例に挙げます。
- 在留資格認定証明書交付申請書:法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
- 申請人の顔写真(4cm×3cm):申請前3ヶ月以内に撮影したもの。
- 返信用封筒:定形封筒に宛名を明記し、切手を貼付したもの。
- 身分関係を証明する文書:
- 配偶者の場合:婚姻証明書、戸籍謄本など
- 子の場合:出生証明書、戸籍謄本など
※外国語の文書には日本語訳が必要です。
- 扶養者の在留カードとパスポートのコピー
- 扶養者の職業及び収入を証明する文書:
- 在職証明書:勤務先で発行してもらいます。
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分):市役所等で取得します。総所得と納税状況が記載されているものが必要です。
※上記はあくまで一例です。個別の状況により、追加で預金残高証明書や理由書などの提出を求められる場合があります。 申請前には必ず出入国在留管理庁の公式サイトで最新の情報を確認してください。
知っておきたい注意点と「資格外活動許可」について
無事に家族滞在ビザを取得できた後も、安心して日本での生活を続けるためには、いくつかの重要な注意点があります。特に、就労に関するルールは厳格に定められており、違反すると厳しい罰則の対象となる可能性があります。また、扶養者との関係に変化があった場合の手続きも見落とせません。ここでは、家族滞在ビザで生活する上での注意点と、働くために必要な「資格外活動許可」について詳しく解説します。
原則就労不可!働くためには「資格外活動許可」が必須
繰り返しになりますが、家族滞在ビザは就労を目的とする在留資格ではありません。 そのため、収入を得る活動(アルバイト、パートタイムなど)を行うことは原則として禁止されています。
もし働くことを希望する場合は、必ず事前に出入国在留管理庁で「資格外活動許可」を申請し、許可を得る必要があります。 この許可を得ることで、以下の条件の範囲内で就労が認められます。
- 就労時間:1週間に28時間以内
- 活動内容:風俗営業等、法律で禁止されている業務を除く
この時間制限は厳守しなければなりません。複数のアルバイトを掛け持ちする場合も、合計時間が週28時間を超えないように注意が必要です。許可を得ずに働いたり、時間を超えて働いたりした場合は「不法就労」となり、本人だけでなく雇用主も罰せられる可能性があります。
扶養者との離婚・死別後の手続き
家族滞在ビザは、扶養者との関係が存続していることが大前提です。そのため、万が一、扶養者である配偶者と離婚または死別した場合は、その時点で家族滞在ビザの要件を満たさなくなります。
この場合、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。そして、引き続き日本での滞在を希望するのであれば、速やかに他の在留資格(「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ)への変更申請を行わなければなりません。 この手続きを怠ると、在留資格が取り消されたり、オーバーステイ(不法滞在)になったりする恐れがあるため、非常に重要です。
在留期間の更新は扶養者と同時に
家族滞在ビザの在留期間は、扶養者の在留期間を超えて許可されることはありません。 基本的には、扶養者の在留期間満了日に合わせて設定されます。したがって、在留期間を更新する際は、原則として扶養者と一緒に更新申請を行う必要があります。
扶養者が更新を忘れていたり、何らかの理由で更新が不許可になったりした場合は、家族滞在ビザも更新できず、家族全員が帰国しなければならない事態に陥る可能性があります。在留カードに記載されている在留期間満了日は、家族全員で常に確認し、早め(通常は3ヶ月前から申請可能)に更新手続きを行うようにしましょう。
まとめ
この記事では、日本で働く外国人の方が家族を呼び寄せるための「家族滞在ビザ」について、その全体像を詳しく解説してきました。要件から申請手続き、そして在留中の注意点まで、多岐にわたる内容でしたが、重要なポイントを改めて振り返ってみましょう。
- ✔ 対象は「配偶者」と「子」のみで、親や兄弟は該当しません。
- ✔ 扶養者の十分な「経済力」の証明が審査の鍵となります。
- ✔ 子が成年に近い場合は、日本で扶養を受ける必要性を具体的に説明する必要があります。
- ✔ 働く場合は、必ず「資格外活動許可」を取得し、週28時間のルールを守る必要があります。
- ✔ 離婚や死別など、扶養者との関係に変化があれば、速やかな手続きが不可欠です。
家族滞在ビザの申請は、ご自身で進めることも不可能ではありません。しかし、書類の準備は煩雑で、個々の状況に応じた的確な対応が求められます。特に、扶養能力の証明や理由書の作成など、専門的な知識がなければ難しい場面も少なくありません。一度不許可になると、その後の再申請のハードルはさらに上がってしまいます。
大切なご家族との日本での生活をスムーズにスタートさせるために、少しでも不安を感じたら、ぜひ一度、ビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。専門家は、最新の法令や審査の傾向を踏まえ、あなたの状況に最適なアドバイスとサポートを提供します。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 

-
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

-
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

-
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

-
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 

-
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。


-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る