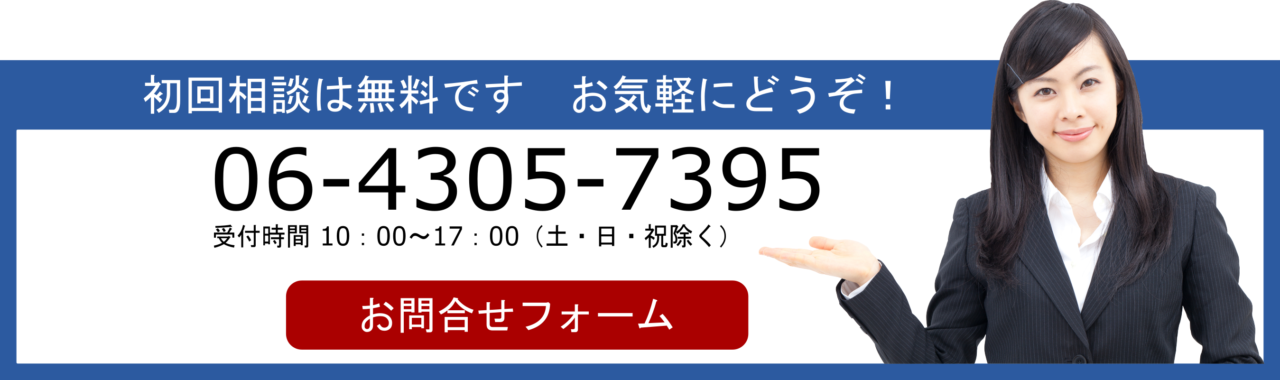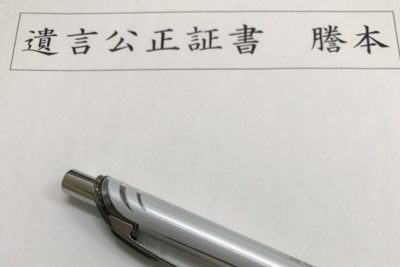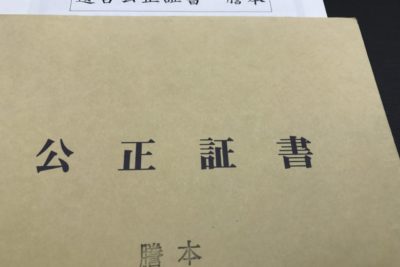遺贈と死因贈与の違い
遺言書作成サポート

遺言書を作成しようと色々と調べる中、「相続」や「遺贈」「死因贈与」などの用語が出てくると思います。
どの用語も死亡によって遺産を承継する制度という点では同じですが、(共通する部分は多いものの)法律的には全く別の制度です。
こちらの記事では、これらの中でも分かりにくい「遺贈」「死因贈与」について、それぞれどんな制度か、共通点、相違点などについてみていきたいと思います。
遺贈(いぞう)とは
「遺贈」とは、遺言によって遺言者の財産を特定の人に譲ることです。
遺言がなければ、相続財産は法定相続人しか受け取ることができませんが、遺言することで法定相続人以外の人(友人、知人や団体など)に「遺贈」することが可能となります。
遺贈は単独行為ですので、遺言者が一方的に「誰々にこれを遺贈する」と意思表示することで、その内容で法律効果が生じます。
死因贈与(しいんぞうよ)とは
「贈与」とは、契約によって契約により成り立ちます。
つまり、財産を相手方に与える意思を示し、相手方がそれを受諾することによってはじめて成り立ちます。
「死因贈与」とは、死亡が原因となって発生する贈与であり、「私が死んだらコレをあなたに譲ります」「はい、分かりました」と両者が合意して初めて成立します。
未成年者に死因贈与を行う場合、死因贈与は契約なので、その未成年者の親権者(法定代理人)の合意を得るか、親権者が代理で行わなければなりません。
遺贈と死因贈与の違い
遺贈は、遺贈者(あげる側の人)が一方的に行う意思表示なので、受遺者(もらう側の人)が受け取らないという選択もできます。
これに対し、死因贈与は贈与者(あげる側の人)と受贈者(もらう側の人)の合意で成立した契約なので、贈与者の死後、受贈者の意思だけでは受取を放棄することはできません。
遺贈には遺言書が必要ですが、死因贈与には両者の合意(口頭での契約も成立するとされていますが、対外的なことを考えると後々のトラブルを回避するため書面が必要)が必要となります。
遺言書と死因贈与契約書が両方ある場合
遺言書でAに相続させるとし、死因贈与契約書でBに贈与するとしたものが同時に存在している場合、どちらが優先されるでしょうか?
原則として、「日付の新しい方」が優先されることになります。新しいもので古いものの抵触する部分を取消した、という考え方です。
ただし、「負担付死因贈与(贈与を受ける者が法律上の義務を負う契約)」の場合で、受贈者が既にその義務を実行していたときは、負担付贈与が優先されます。
まとめ
「遺贈」と「死因贈与」、違いを理解いただけたと思います。
遺言書のなかで使う言葉とすれば「遺贈」で、「~に〇〇を遺贈する。」という文言になります。(「〇〇を死因贈与する。」とはなりません。)
遺言書の作成は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
遺言書(案)を作成いたします
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
ぜひ、専門家にご相談ください。
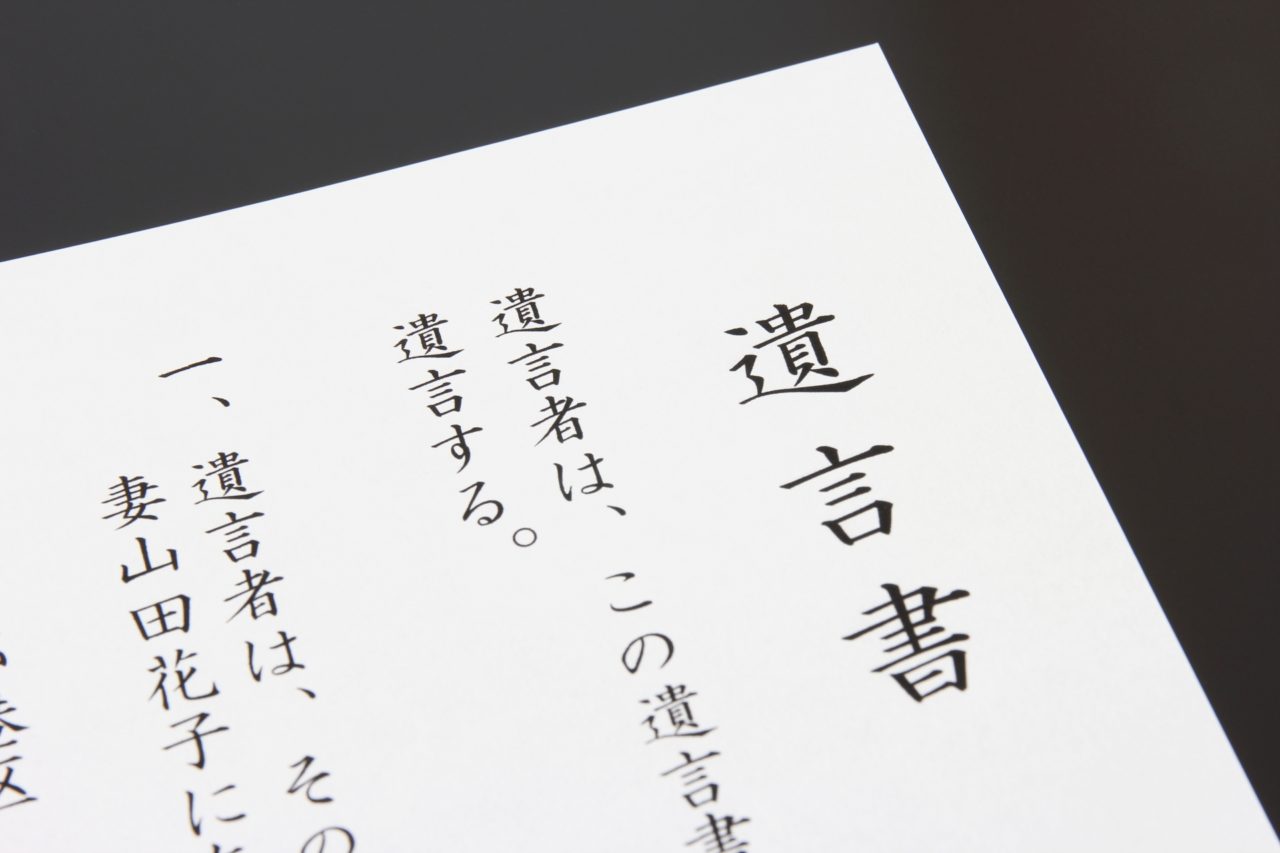
財産目録を作成いたします
相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。

証人へ就任いたします(公正証書遺言)
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。