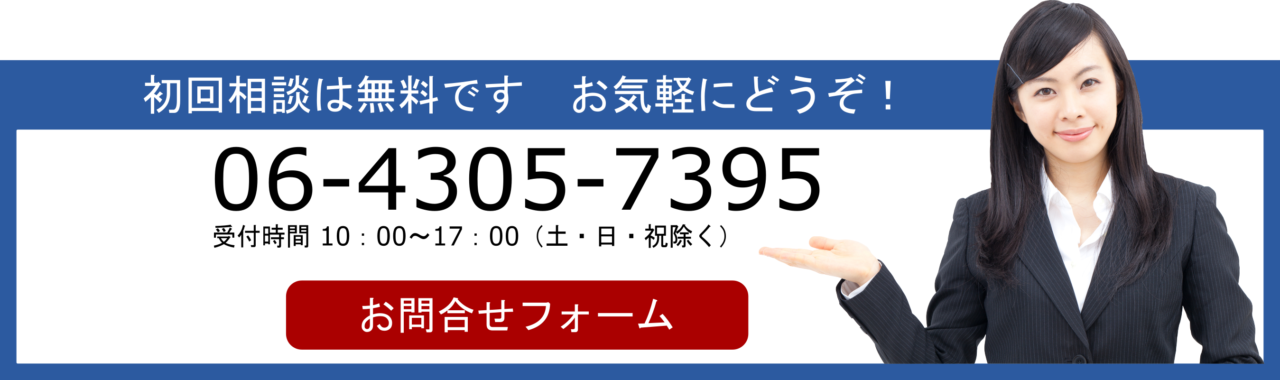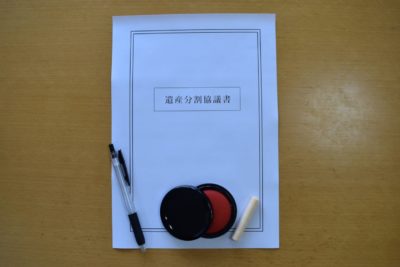相続における『失踪宣告』とは
相続サポート

失踪宣告とは
失踪宣告がなされるうえで、失踪は次の2つに分かれます。
- 普通失踪
- 危難失踪
不在者(行方不明者)の生死が7年間明らかでない場合は、普通失踪となります。
一方、戦争や船舶の沈没、震災などの危難(災難)に遭遇した場合に、その危難が去ってからも1年間不在者の生死が明らにならないときは、危難失踪となります。
これらの失踪が認められる場合に家庭裁判所は申立てにより失踪宣告をすることができるという制度です。
失踪宣告がなされると、その不在者は法律上死亡したものとみなされます。
普通失踪と危難失踪では、死亡したものとみなされる時期が異なります。
| 失踪宣告の申立てができる時期 | 死亡したものとみなされる時期 | |
| 普通失踪 | 不在者の生死が7年間明らかでないとき | 生死が明らかでなくなってから7年間経過したとき |
| 危難失踪 | 戦争、船舶の沈没、その他死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、そのぞれの原因となる事象が去った後1年間明らかでないとき | 危難が去ったとき |
相続の場面で失踪宣告が必要になるのは相続人のどなたかが行方不明のときです。
相続人のどなたかが行方不明であるということは、遺産分割協議を行うことができません(相続人全員の参加でなければ、その遺産分割協議は無効となります。)。
遺産分割協議を行うことができなければ、その後の相続手続きを進めることができませんので、他の相続人にとっては大変困った状況になるかと思います。
このような場面で失踪宣告制度を利用することにより、不在者を相続人から除外することで、遺産分割協議に段階を進めることができるようになります。
失踪宣告の申立てができる人は?
不在者財産管理人の申立てができるのは以下に該当する利害関係者です。
- 不在者の配偶者
- 相続人
- 不在者財産管理人
- その他失踪宣告を求めるについて法律上の利害関係を有する者
失踪宣告の申立て先は?
申立ては、不在者の従来の住所地もしくは居住地の家庭裁判所に対して行います。
申立てに必要な書類
失踪宣告の申立てをする場合、以下のものを用意する必要があります。
- 申立書(収入印紙800円分を添付)
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証明する資料(不在者の捜査願受理証明書、返却された不在者宛ての手紙など)
- 申立人の利害関係を証明する資料(親族であれば戸籍謄本(全部事項証明書など))
失踪宣告の申立ての手続の流れ
申立てから失踪宣告までは以下のような流れになります。
1.申立て
![]()
2.調査
![]()
3.勧告
![]()
4.失踪宣告
失踪宣告後に必要な手続き
審判が確定(失踪宣告)してから10日以内に、市区町村役場(不在者の本籍地又は申立人の住所地)に失踪の届出をしなければなりません。
この届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので、事前に審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付申請(郵送可)をする必要があります。
まとめ
- ✔ 相続人に行方不明者がいる場合に失踪宣告という手段がある。
- ✔ 失踪宣告の申立てをするには一定の条件がある
- ✔ 失踪宣告は家庭裁判所に申し立てをする。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
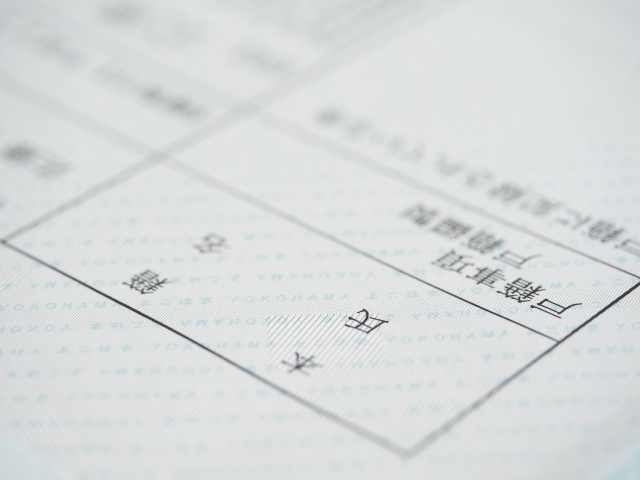
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
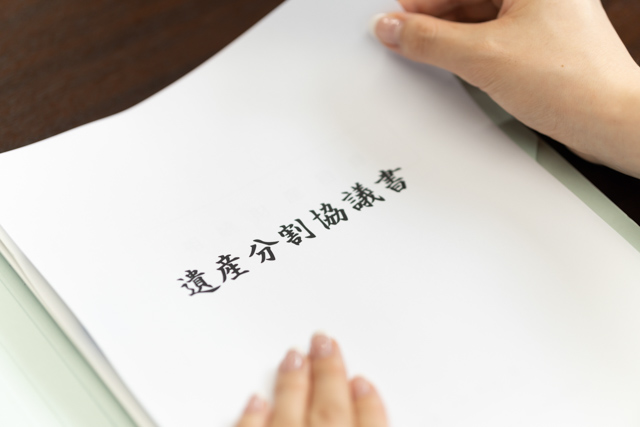
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。