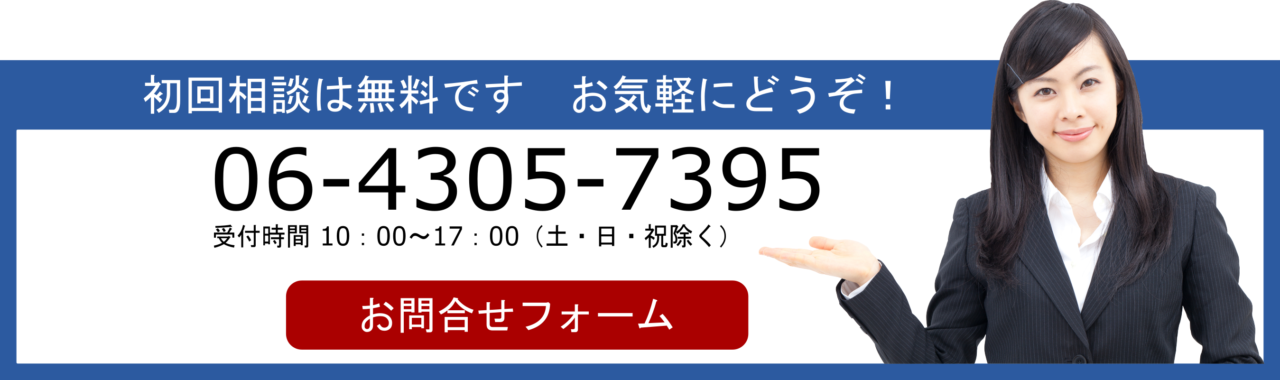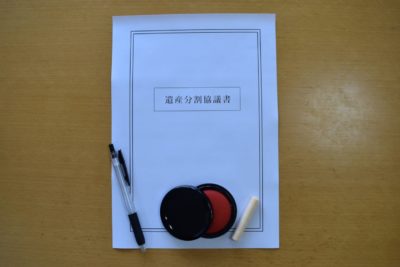特別縁故者とは?
相続サポート

相続の場面で、有効な遺言書が残されていない場合、故人の遺産は法定相続人が相続するのが原則です。
しかし、例外的に法定相続人以外の人が財産の分与を受けることができる場合があります。
「特別縁故者」が、この例外的に相続できる人に当たります。
特別縁故者とは
亡くなった人に法定相続人がいない場合や法定相続人全員が相続放棄をした場合は、通常その人の財産は国庫に帰属され国のものになります。
しかし、民法は下記に該当する人を「特別縁故者」として、請求があれば相続財産の全部又は一部を与えることができると規定しています。(民法 958条の3)
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- 被相続人と特別の縁故があった者
1.生計を同じくしていた者
いわゆる内縁の妻や夫、未認知の子、叔父や叔母など法定相続人でない親族などで、被相続人と生計を一にしていた者(つまり、同じ財布で生活していた者)は、特別縁故者とみなされる可能性があります。
“可能性”と書いたのは、生計を同じくしていた者は、その事実をもって即、特別縁故者となるわけではなく、家庭裁判所により認められることによって特別縁故者となるからです(後述)。
2. 被相続人の療養看護に努めた者
被相続人の療養看護に努めた人は、特別縁故者として認められる可能性があります。
ただし、一般的な親類縁者が求められるであろう範囲のお世話では、特別縁故者としては認められません。
又、報酬以上に献身的に看護に尽くした看護婦が特別縁故者として認められた例もあります。
3.被相続人と特別の縁故があった者
「特別の縁故」とは、漠然として表現ですが、「被相続人と精神的・物質的に密接な関係にあった者で、相続財産を分け与えることが被相続人の意思に合致するであろう者」とされています。
自然人のみならず法人(学校法人、宗教法人、老人ホーム、市町村など)でも特別縁故者になり得ます。
特別縁故者の申立
⑴ 特別縁故者の申立先
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
⑵ 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
⑶ 申立てに必要な書類
- 申立書
- 申立人の住民票又は戸籍附票
特別縁故者として遺産取得する場合の流れ
特別縁故者として財産の分与を受けるには、家庭裁判所に選定されることが必要になります。次のような流れで手続を進めていきます。
- 相続財産管理人の選任
- 清算手続きと相続人の捜索
- 財産分与の申立
- 特別縁故者の認定
1.相続財産管理人の選任
相続人がいない場合、相続財産を管理するために選任の人を立てる必要があります。これが「相続財産管理人」制度です。
特別縁故者は、自らが「相続財産管理人」になることはできないため候補者を立て、家庭裁判所に申立てをします。
2.清算手続きと相続人の捜索
相続財産管理人は、債権者や受遺者の有無、相続人の有無を確認するため法定された一定の期間以上官報に公告します。
3.財産分与の申立
上記の期間内に名乗り出る者がいなかった場合に、特別縁故者の財産分与の申立てができます。
申立てができるのは、相続人を確認するための公告期間満了以降で、かつその期間が満了してから3カ月以内です。
4.別縁故者の審判
申立てをした者が、特別縁故者に当たるか否か、相続財産をどのように分与するかを家庭裁判所が審判し判断します。
まとめ
以上、特別縁故者について説明させていただきました。
みなとまち行政書士事務所では相続に関するご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
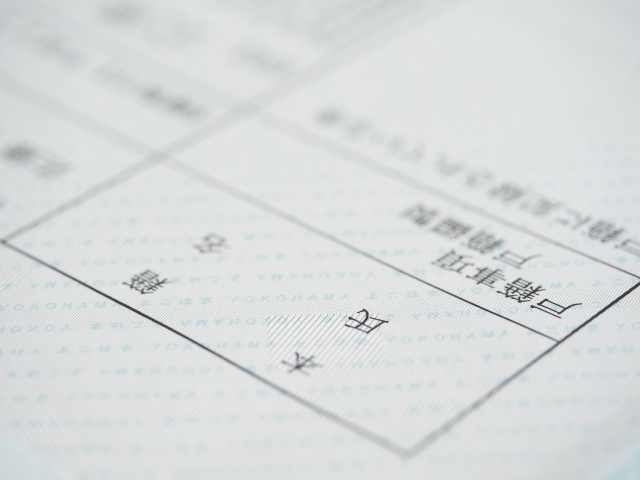
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
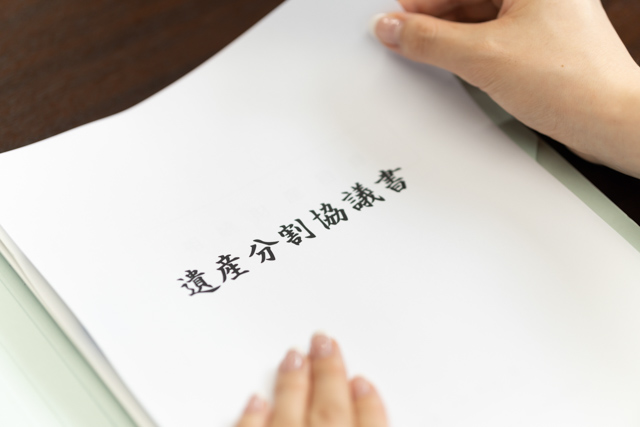
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。